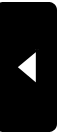2009年06月13日
「伏見桃片伊万里」13
母親も、おぼろげ事情はわかったらしい。
階下では芯張り棒をはずして外に出る気配がした。水音。井戸水を汲んで水瓶を満たし、竃に火をおこし、鍋いっぱいに湯を沸かしてくれているらしい。
「まったく、何て晩だ」
吐寫にまみれた隼人の着物を脱がせ、体を湯で拭き、着替えさせた。
(後は、こいつの運次第)ということになる。
時が移った。微弱だった脈が、しっかりしてきた。圭吾は隼人の手首を離した。
「酒毒か・・」圭吾が、深い吐息を吐いた。
世間知らずの圭吾は、今の今まで、酒毒とは酒を飲み続けて数十年を経てなるものと思い込んでいた。酒を口にして四年に満たぬ隼人の問題飲酒が、ここまで病根の深いものだったとは。各々の口にする酒量が心身にどれほどの影響を与えるのか、また与えずにすむのか、幅広い個人差というものがあるのだということを―医者として思い知った。
実は現代でも、アルコール依存の治療を受けている十代から二十代の患者は決して少なくないのである。一般に若年者ほどアルコール依存の進行は早く、重篤な危機を招き易いことは、もっと広く知られてもよいであろう。
「ああ完全にな。酒毒はすすむと、気分をひどく鬱屈させるだろ」
「鬱屈して、あげく医者が砒素か」
「首括ってりゃ、死に損なわなかったか」
「圭吾!」
「すまん、冗談言ってる場合じゃないな」
「酒毒がここまで回ってるなら・・」
「暴れるな。それとも、今度こそ、首でもくくるかもしれん」
「自傷他害のおそれ大、だな。傍を離れるわけいかんな」うなずき合う。
(ん・・)飯の炊けるにおいがした。味噌の香りも。急に、激しい空腹を感じた。
「有難い。あの母親、朝飯の仕度をしてくれているらしいぞ」慎一郎が立ち上がった。
「朝飯・・」圭吾も立つ。雨戸を開けた。
「もう夜が明けてる・・天気はよさそうだ」
東の空が、薄墨色、ほの明るい。
「さあ、腹ごしらえしよう」
階下では芯張り棒をはずして外に出る気配がした。水音。井戸水を汲んで水瓶を満たし、竃に火をおこし、鍋いっぱいに湯を沸かしてくれているらしい。
「まったく、何て晩だ」
吐寫にまみれた隼人の着物を脱がせ、体を湯で拭き、着替えさせた。
(後は、こいつの運次第)ということになる。
時が移った。微弱だった脈が、しっかりしてきた。圭吾は隼人の手首を離した。
「酒毒か・・」圭吾が、深い吐息を吐いた。
世間知らずの圭吾は、今の今まで、酒毒とは酒を飲み続けて数十年を経てなるものと思い込んでいた。酒を口にして四年に満たぬ隼人の問題飲酒が、ここまで病根の深いものだったとは。各々の口にする酒量が心身にどれほどの影響を与えるのか、また与えずにすむのか、幅広い個人差というものがあるのだということを―医者として思い知った。
実は現代でも、アルコール依存の治療を受けている十代から二十代の患者は決して少なくないのである。一般に若年者ほどアルコール依存の進行は早く、重篤な危機を招き易いことは、もっと広く知られてもよいであろう。
「ああ完全にな。酒毒はすすむと、気分をひどく鬱屈させるだろ」
「鬱屈して、あげく医者が砒素か」
「首括ってりゃ、死に損なわなかったか」
「圭吾!」
「すまん、冗談言ってる場合じゃないな」
「酒毒がここまで回ってるなら・・」
「暴れるな。それとも、今度こそ、首でもくくるかもしれん」
「自傷他害のおそれ大、だな。傍を離れるわけいかんな」うなずき合う。
(ん・・)飯の炊けるにおいがした。味噌の香りも。急に、激しい空腹を感じた。
「有難い。あの母親、朝飯の仕度をしてくれているらしいぞ」慎一郎が立ち上がった。
「朝飯・・」圭吾も立つ。雨戸を開けた。
「もう夜が明けてる・・天気はよさそうだ」
東の空が、薄墨色、ほの明るい。
「さあ、腹ごしらえしよう」
Posted by 渋柿 at 09:16 | Comments(0)
2009年06月12日
「伏見桃片伊万里」12
圭吾は母親に向き直った。
「まだ暫くは大人しくしている方がよいが。寝かせておく所、あてはあるかね」
母親はしばらく黙っていた。
「よう効くお薬どすなあ」
娘の寝髪の後れ毛を直しながら言う。
「これは―砒素というのは、薬というより毒なのだが」
「毒ぅ!」母親が仰天する。
「あ、いや。薬と言うものは、本来すべて毒なのだ」慎一郎が、圭吾の舌足らずを補った。
「はあ」
「その毒を薄めて、薬にするのが医者の仕事でな。もっとも砒素は正真正銘の猛毒で、鼠獲りにするぐらいじゃ。人に使うのは、今夜のように切羽詰ったときだけ・・ギリギリの、ごく僅かの量だけなあ―」
慎一郎の言葉に反応して、パッと圭吾が立ち上がった。慎一郎も気付いた。階段を駆け上り、障子を開けた。有明行灯のみ仄かな、うす闇の中。
やはり、であった。
砒素など、駆出しが通常薬籠で持ち歩くものではない。隼人は、布団の上に倒れていた。
手に、空の油紙が残っている。
(砒素を呑んだ―)
(やりあがった)
二人は階段を駆け下りて、土間の台所の水瓶から、鍋と釜いっぱいに水を汲んだ。漏斗を使えばなおいいが、探している時間は無い。
圭吾が隼人を抱えあげ、無理に口をこじ開けた。そこへ、慎一郎が鍋と釜の水を流し込む。それから、慎一郎が鳩尾を押し、水とともに胃の腑の砒素を吐かせた。吐瀉。酒精と胃液の、物凄い臭いがした。失禁も、しているようだ。慎一郎が吐寫させている間に、圭吾は蝋燭を点す。
一回では足らぬ。何回も階下から水を運ぶ。
「まだ暫くは大人しくしている方がよいが。寝かせておく所、あてはあるかね」
母親はしばらく黙っていた。
「よう効くお薬どすなあ」
娘の寝髪の後れ毛を直しながら言う。
「これは―砒素というのは、薬というより毒なのだが」
「毒ぅ!」母親が仰天する。
「あ、いや。薬と言うものは、本来すべて毒なのだ」慎一郎が、圭吾の舌足らずを補った。
「はあ」
「その毒を薄めて、薬にするのが医者の仕事でな。もっとも砒素は正真正銘の猛毒で、鼠獲りにするぐらいじゃ。人に使うのは、今夜のように切羽詰ったときだけ・・ギリギリの、ごく僅かの量だけなあ―」
慎一郎の言葉に反応して、パッと圭吾が立ち上がった。慎一郎も気付いた。階段を駆け上り、障子を開けた。有明行灯のみ仄かな、うす闇の中。
やはり、であった。
砒素など、駆出しが通常薬籠で持ち歩くものではない。隼人は、布団の上に倒れていた。
手に、空の油紙が残っている。
(砒素を呑んだ―)
(やりあがった)
二人は階段を駆け下りて、土間の台所の水瓶から、鍋と釜いっぱいに水を汲んだ。漏斗を使えばなおいいが、探している時間は無い。
圭吾が隼人を抱えあげ、無理に口をこじ開けた。そこへ、慎一郎が鍋と釜の水を流し込む。それから、慎一郎が鳩尾を押し、水とともに胃の腑の砒素を吐かせた。吐瀉。酒精と胃液の、物凄い臭いがした。失禁も、しているようだ。慎一郎が吐寫させている間に、圭吾は蝋燭を点す。
一回では足らぬ。何回も階下から水を運ぶ。
Posted by 渋柿 at 19:16 | Comments(0)
2009年06月12日
「伏見桃片伊万里」11
「船着場で、あの、伏見から来たいうお人に頂いて。元は九州の伊万里んもんやて」
母親は、小さい声で言った。
(これも伊万里と言えば伊万里といえんこともないが。お菰をからかうなど、どこの誰だ、罪作りな)
「いやあ、伏見は桃の名所・・芭蕉や蕪村も名句を詠んでおる。この紅斑は点々と桃の花びら、白磁はほんのりと紅を帯びて、淀川の、伏見の桃の盛りの風情じゃなあ」相手の目が見られず、殆どしどろもどろであった。
「はい、優しい色で。この器に、えらい慰めてもらいました」母親は嬉しそうに微笑む。
「けっ、知らぬが仏、か」隼人が毒付く。
「おい!」
「馬鹿はほっとけ、圭吾」
いつもの大酒の上をいく量だ。
「もう、二階へ行って寝ろ」叱り付ける。
「そう、する」
今夜は、一旦酔いつぶれた後の連続飲酒じみた大酒である。隼人の体内には、いつもの大酒の上をいく量の酒精が溜まっている。
「もう、用もないだろ」
自分の薬籠を下げて、階段を登ろうとした。 ガン。一段目で蹴躓いてつんのめった。
「大丈夫か」
「まあ、大丈夫じゃないだろうが・・大丈夫かなあ。うん、大丈夫だ。―俺はもう、駄目だな」隼人はそれでも何とか階段を登り、寝部屋にたどり着いたようだった。
母親は、小さい声で言った。
(これも伊万里と言えば伊万里といえんこともないが。お菰をからかうなど、どこの誰だ、罪作りな)
「いやあ、伏見は桃の名所・・芭蕉や蕪村も名句を詠んでおる。この紅斑は点々と桃の花びら、白磁はほんのりと紅を帯びて、淀川の、伏見の桃の盛りの風情じゃなあ」相手の目が見られず、殆どしどろもどろであった。
「はい、優しい色で。この器に、えらい慰めてもらいました」母親は嬉しそうに微笑む。
「けっ、知らぬが仏、か」隼人が毒付く。
「おい!」
「馬鹿はほっとけ、圭吾」
いつもの大酒の上をいく量だ。
「もう、二階へ行って寝ろ」叱り付ける。
「そう、する」
今夜は、一旦酔いつぶれた後の連続飲酒じみた大酒である。隼人の体内には、いつもの大酒の上をいく量の酒精が溜まっている。
「もう、用もないだろ」
自分の薬籠を下げて、階段を登ろうとした。 ガン。一段目で蹴躓いてつんのめった。
「大丈夫か」
「まあ、大丈夫じゃないだろうが・・大丈夫かなあ。うん、大丈夫だ。―俺はもう、駄目だな」隼人はそれでも何とか階段を登り、寝部屋にたどり着いたようだった。
Posted by 渋柿 at 06:55 | Comments(0)
2009年06月11日
「伏見桃片伊万里」10
汚れてはいるが、母子とも顔立ちは整い、言葉遣いにも品があった。お菰の境遇に落ちるには、仔細があったらしい、と圭吾は思った。
「お足は、またでいいよ」
「お菰から金は取れねえよ」隼人が横から大声を出した。
「隼人!」
「そのうち、また発作は起きる。安心しな、そんときゃよ、また、ここに来りゃいい。立派なお医者様が二人、必ず診てくれる筈さ」
「お前!」
圭吾と慎一郎が必死の処置をしている間も、隼人は土間の台所辺りを徘徊していた。「おい、焼酎は消毒用だぞ」と声はかけたが、馬耳東風だった。
「喘息に傷口の消毒はなかろう」
「勝手にしろ!あとで買って返せよ」
「馬鹿!こいつ酒屋にやった日にゃ剣呑だ」
全く・・とは思ったが、それ以上かまっている余裕はなかった。それをいいことに・・台所の焼酎まで呑尽くしたらしい。
「あの、これを」母親が、黄ばんだ手拭の包みを差し出した。「お恥ずかしゅうて。こんなんしか。お願い、受けてくだはいまへんやろか、伏見たら伊万里のなんたらやて、貰うたんどすけど」
母親が手拭を開いた。磁器?もしや高価な品か?寄席の噺のような―期待は、外れた。
(なんのことだ)ぼってりと厚い。
本来薄く繊細であるべき伊万里とは似ても似つかぬ、大小二つの鉢であった。いや、どんぶり鉢というべきか。
「こりゃいい」隼人が嗤った。「わはは、まったく、こりゃあいいぜ。おい圭吾、お前が貰っとけ。ここは元々お前の家だしなあ」
「好い加減にしろ!」
二つとも同じ窯で焼かれた、本来は白磁に藍の染付であろう。だが全体に赤みがあり、点々と紅斑が入っている。描画の線も不鮮明で、本来鮮やかな藍色に仕上がらねばならぬはずが、紅い。絵も稚拙で、何を描いているのかはっきりしない。
(蛸唐草とも違う、なあ。はて?)
「そう、伏見か」口の中の呟きであった。
(くらわんか、か)
「お足は、またでいいよ」
「お菰から金は取れねえよ」隼人が横から大声を出した。
「隼人!」
「そのうち、また発作は起きる。安心しな、そんときゃよ、また、ここに来りゃいい。立派なお医者様が二人、必ず診てくれる筈さ」
「お前!」
圭吾と慎一郎が必死の処置をしている間も、隼人は土間の台所辺りを徘徊していた。「おい、焼酎は消毒用だぞ」と声はかけたが、馬耳東風だった。
「喘息に傷口の消毒はなかろう」
「勝手にしろ!あとで買って返せよ」
「馬鹿!こいつ酒屋にやった日にゃ剣呑だ」
全く・・とは思ったが、それ以上かまっている余裕はなかった。それをいいことに・・台所の焼酎まで呑尽くしたらしい。
「あの、これを」母親が、黄ばんだ手拭の包みを差し出した。「お恥ずかしゅうて。こんなんしか。お願い、受けてくだはいまへんやろか、伏見たら伊万里のなんたらやて、貰うたんどすけど」
母親が手拭を開いた。磁器?もしや高価な品か?寄席の噺のような―期待は、外れた。
(なんのことだ)ぼってりと厚い。
本来薄く繊細であるべき伊万里とは似ても似つかぬ、大小二つの鉢であった。いや、どんぶり鉢というべきか。
「こりゃいい」隼人が嗤った。「わはは、まったく、こりゃあいいぜ。おい圭吾、お前が貰っとけ。ここは元々お前の家だしなあ」
「好い加減にしろ!」
二つとも同じ窯で焼かれた、本来は白磁に藍の染付であろう。だが全体に赤みがあり、点々と紅斑が入っている。描画の線も不鮮明で、本来鮮やかな藍色に仕上がらねばならぬはずが、紅い。絵も稚拙で、何を描いているのかはっきりしない。
(蛸唐草とも違う、なあ。はて?)
「そう、伏見か」口の中の呟きであった。
(くらわんか、か)
Posted by 渋柿 at 11:43 | Comments(0)
2009年06月10日
「伏見桃片伊万里」9
圭吾が寝部屋から、薬籠を抱えてくる。
「隼人、砒素はどこだ」
「四段目の、右」
確かに、決まりのものとは別に、小さな油紙に包まれた粉末があった。圭吾と慎一郎は慎重に調合した。焦る手に、粉末がしばしばこぼれる。砒素とは、鶏冠石からとれる劇薬である。ごく微量の砒素は喘息発作の、粘度の高い痰が詰り狭窄した気道を広げる。常用すれば危険だが、危機的状況下では劇的な特効薬でもあるのだ。娘の体力は尽きかけている。咳が、弱々しい喘ぎに変わっている。二度三度、薬が天秤皿からこぼした。焦るな!と思う。だが・・「ヒ―ッ」と娘ののどが鳴り、全身が痙攣した。
飲み下しさえくれれば!
娘は、何とか薬を嚥下した。
背中をさすり続け一刻が過ぎ、娘の喘鳴が消え、咳が収まった。肩の上下が止まり、呼吸も少しずつ穏やかになる。頬に血の気が戻ってきた。やがて、母親にもたれ、寝入る。
「もう大丈夫だ」
「おおきに、有難うさんでございました」
母親が、放心したように頭を下げた。
娘を布団に、そっと横たえる。
「やっぱり、この子、喘息やったんどすか」
「今まで、医者に―」見せたことがあるか、と聞きかけて止める。
「よう風邪を引く子やとは思うてました。治りもひどう悪うて。咳は辛そうで、見とるこっちも辛うおまして。でも我慢させて。けど、こんなんひどいんは初めてどす」
「咳がひどくなったときは、体を冷やさぬ静かなところで休ませて、水気を与えて、とにかく痰を切らせることだ。背中を叩いてもよい。本当は、こんなになる前に発作を鎮めるのが肝心なんだが。息が詰まらぬよう、それだけ用心をして、時を待つ。凌いでいるうちに、そう十一、二にもなれば」
「治るんどすか」
「ああ、大丈夫だ」
「子供の喘息は、大きくなれば大概自分の力で抑え込める。そのときそのとき、発作をなんどかやり過ごしていたら、時は来る。きっと治る」慎一郎も言葉を添える。
「また、こんなんこと、何度もあるんだっしゃろか?」
「とにかく、ここまでひどい発作だけは起こさないよう、それだけさ。日頃体を乾いた布でこするのもいい。それとなるべく滋養のあるものを」
母親は、しばらく俯いていた。
「あの、お薬礼んことどすけど―」母親は口ごもった。
「隼人、砒素はどこだ」
「四段目の、右」
確かに、決まりのものとは別に、小さな油紙に包まれた粉末があった。圭吾と慎一郎は慎重に調合した。焦る手に、粉末がしばしばこぼれる。砒素とは、鶏冠石からとれる劇薬である。ごく微量の砒素は喘息発作の、粘度の高い痰が詰り狭窄した気道を広げる。常用すれば危険だが、危機的状況下では劇的な特効薬でもあるのだ。娘の体力は尽きかけている。咳が、弱々しい喘ぎに変わっている。二度三度、薬が天秤皿からこぼした。焦るな!と思う。だが・・「ヒ―ッ」と娘ののどが鳴り、全身が痙攣した。
飲み下しさえくれれば!
娘は、何とか薬を嚥下した。
背中をさすり続け一刻が過ぎ、娘の喘鳴が消え、咳が収まった。肩の上下が止まり、呼吸も少しずつ穏やかになる。頬に血の気が戻ってきた。やがて、母親にもたれ、寝入る。
「もう大丈夫だ」
「おおきに、有難うさんでございました」
母親が、放心したように頭を下げた。
娘を布団に、そっと横たえる。
「やっぱり、この子、喘息やったんどすか」
「今まで、医者に―」見せたことがあるか、と聞きかけて止める。
「よう風邪を引く子やとは思うてました。治りもひどう悪うて。咳は辛そうで、見とるこっちも辛うおまして。でも我慢させて。けど、こんなんひどいんは初めてどす」
「咳がひどくなったときは、体を冷やさぬ静かなところで休ませて、水気を与えて、とにかく痰を切らせることだ。背中を叩いてもよい。本当は、こんなになる前に発作を鎮めるのが肝心なんだが。息が詰まらぬよう、それだけ用心をして、時を待つ。凌いでいるうちに、そう十一、二にもなれば」
「治るんどすか」
「ああ、大丈夫だ」
「子供の喘息は、大きくなれば大概自分の力で抑え込める。そのときそのとき、発作をなんどかやり過ごしていたら、時は来る。きっと治る」慎一郎も言葉を添える。
「また、こんなんこと、何度もあるんだっしゃろか?」
「とにかく、ここまでひどい発作だけは起こさないよう、それだけさ。日頃体を乾いた布でこするのもいい。それとなるべく滋養のあるものを」
母親は、しばらく俯いていた。
「あの、お薬礼んことどすけど―」母親は口ごもった。
Posted by 渋柿 at 20:28 | Comments(0)
2009年06月10日
「伏見桃片伊万里」8
慎一郎と圭吾は目を見交わせた。慎一郎が、努めて母子を怯えさせぬよう、穏やかに言った。隼人を叱りつける時とは別人の優しい声音であった。こんな時、童顔は役に立つ。
「実は今、ここではろくな治療が出来ぬのじゃ。ここは私達が寝泊りする場でな、薬がおいてない。治療所はここから少し離れておってな。今から薬を取りにまいらねばならぬ。あ、いや、娘御は動かさぬがよい。急いで行ってまいる。ここで暫く待って欲しい」
その間に圭吾も、己が膝に移した娘の背を、叩くように強く摩擦し続けた。
「大丈夫、行くのはこの男だけだ」
娘は喘ぐ。喉の奥、引きつる音がした。
(せめて、痰が出れば―慎一郎が治療所まで走るとして、それを待って、それから薬を調合して―)いや、間に合うまい、たぶん。
「どうか、助けて。お願いいたします、お願いどす」母親が、頭を畳に擦り付けた。
「では」慎一郎は立ち上がった。「心配要らぬ。すぐ戻る」
「間に合わんぞ」突然隼人の声がした。すっかり酔いつぶれていると思っていた。まだろれつは怪しい。
(酔っ払いめ!)圭吾は眉を顰めた。
事態が切迫していることは承知している。その上で最善を尽くそうとしているのだ。
「薬なら、ある」
隼人が、危うい足取りで立ち上がった。
「寝部屋に、俺の薬籠が・・ある」
「おまえ、こっちに薬籠置いているのか」
「ああ」助かった、と圭吾は安堵の息を吐く。
「だが」慎一郎が言いかけて止めた。
これほど激烈な喘息発作を鎮めるには、薬籠の常備薬では足りぬ。おそらく劇薬が必要だろう。
(砒素―か)暗然となる。
「大丈夫、砒素もある」隼人は続けた。
寝部屋へ、階段の方へ行く。ふらつく足取りであった。本当に危うい。
「俺が持って来る」圭吾が立ち上がった。
隼人はストンと尻餅をつく。
「調合も、やってくれ」
「当たり前だ!」圭吾と慎一郎が同時に怒鳴った。砒素は劇薬というより本来猛毒である。酔っ払いに任せられるようなものではない。
「実は今、ここではろくな治療が出来ぬのじゃ。ここは私達が寝泊りする場でな、薬がおいてない。治療所はここから少し離れておってな。今から薬を取りにまいらねばならぬ。あ、いや、娘御は動かさぬがよい。急いで行ってまいる。ここで暫く待って欲しい」
その間に圭吾も、己が膝に移した娘の背を、叩くように強く摩擦し続けた。
「大丈夫、行くのはこの男だけだ」
娘は喘ぐ。喉の奥、引きつる音がした。
(せめて、痰が出れば―慎一郎が治療所まで走るとして、それを待って、それから薬を調合して―)いや、間に合うまい、たぶん。
「どうか、助けて。お願いいたします、お願いどす」母親が、頭を畳に擦り付けた。
「では」慎一郎は立ち上がった。「心配要らぬ。すぐ戻る」
「間に合わんぞ」突然隼人の声がした。すっかり酔いつぶれていると思っていた。まだろれつは怪しい。
(酔っ払いめ!)圭吾は眉を顰めた。
事態が切迫していることは承知している。その上で最善を尽くそうとしているのだ。
「薬なら、ある」
隼人が、危うい足取りで立ち上がった。
「寝部屋に、俺の薬籠が・・ある」
「おまえ、こっちに薬籠置いているのか」
「ああ」助かった、と圭吾は安堵の息を吐く。
「だが」慎一郎が言いかけて止めた。
これほど激烈な喘息発作を鎮めるには、薬籠の常備薬では足りぬ。おそらく劇薬が必要だろう。
(砒素―か)暗然となる。
「大丈夫、砒素もある」隼人は続けた。
寝部屋へ、階段の方へ行く。ふらつく足取りであった。本当に危うい。
「俺が持って来る」圭吾が立ち上がった。
隼人はストンと尻餅をつく。
「調合も、やってくれ」
「当たり前だ!」圭吾と慎一郎が同時に怒鳴った。砒素は劇薬というより本来猛毒である。酔っ払いに任せられるようなものではない。
Posted by 渋柿 at 07:11 | Comments(0)
2009年06月09日
「伏見桃片伊万里」7
「お願いどす、お願い!」突然、戸を激しく叩く音がした。切迫した女の声だった。
「どなたか」慎一郎が訊た。
「こちらにお医者さまがおらはると伺うて参じたもんどす。子供の咳が。咳が止まらへんんどす。苦しがって。お願いします。お助けください」
板戸をへだてて、激しい咳が聞こえた。まだ幼いようだ。そこは医者である。子の刻を廻ったといっても、二人とも潜戸を開けるのに躊躇はなかった。そこにこの寒空にもかかわらぬ、一瞬案山子か、と見紛う姿があった。
目を擦った。
(いや、お菰さん、か)
三つ四つばかりの女児を抱えて入ってきた女は、垢まみれの継接、醤油で煮染めたような襤褸を纏っていた。帯は藁縄である。ぐったりと抱かれている子供も同様であった。
「圭吾、入って頂け」慎一郎に声をかけられ、我に帰った。
「こちらへ」土間に続く居間へ導いた。
「布団、だな」慎一郎が二階の寝部屋から、自分の布団一式を持って来る。
子供は、苦しがって横になるのを嫌がった。涙をこぼしながら、あえいでいる。母親らしい女が、膝の上でひしと抱く。圭吾は小火鉢を敷居の縁まで動かし、炭を熾した。夜半、冷気は身を切る。鍋に水を満たして架けたのは、室内の加湿のためである。
「初めは火から遠ざかった方がよいのだ。炭火の瘴気はよくないでな」慎一郎がいう。
「とにかく、蓑虫だ」隼人の掻巻きを引っぺがし、子供を包んだ。その上に布団を巻いた。
まずは、保温である。
娘は肩で息をしていた。胸に耳を付けるまでもなく、娘が息をするたびに大きく音が聞こえる。もはや体に廻らすに十分な息も出来ないらしく、唇が紫色に変じていた。顔色も同じである。
(喘息の発作だな)
(それもかなり重篤だぞ)
(このままでは、窒息しちまう)
「どなたか」慎一郎が訊た。
「こちらにお医者さまがおらはると伺うて参じたもんどす。子供の咳が。咳が止まらへんんどす。苦しがって。お願いします。お助けください」
板戸をへだてて、激しい咳が聞こえた。まだ幼いようだ。そこは医者である。子の刻を廻ったといっても、二人とも潜戸を開けるのに躊躇はなかった。そこにこの寒空にもかかわらぬ、一瞬案山子か、と見紛う姿があった。
目を擦った。
(いや、お菰さん、か)
三つ四つばかりの女児を抱えて入ってきた女は、垢まみれの継接、醤油で煮染めたような襤褸を纏っていた。帯は藁縄である。ぐったりと抱かれている子供も同様であった。
「圭吾、入って頂け」慎一郎に声をかけられ、我に帰った。
「こちらへ」土間に続く居間へ導いた。
「布団、だな」慎一郎が二階の寝部屋から、自分の布団一式を持って来る。
子供は、苦しがって横になるのを嫌がった。涙をこぼしながら、あえいでいる。母親らしい女が、膝の上でひしと抱く。圭吾は小火鉢を敷居の縁まで動かし、炭を熾した。夜半、冷気は身を切る。鍋に水を満たして架けたのは、室内の加湿のためである。
「初めは火から遠ざかった方がよいのだ。炭火の瘴気はよくないでな」慎一郎がいう。
「とにかく、蓑虫だ」隼人の掻巻きを引っぺがし、子供を包んだ。その上に布団を巻いた。
まずは、保温である。
娘は肩で息をしていた。胸に耳を付けるまでもなく、娘が息をするたびに大きく音が聞こえる。もはや体に廻らすに十分な息も出来ないらしく、唇が紫色に変じていた。顔色も同じである。
(喘息の発作だな)
(それもかなり重篤だぞ)
(このままでは、窒息しちまう)
Posted by 渋柿 at 08:42 | Comments(0)
2009年06月07日
「伏見桃片伊万里」6
塾の勉学は厳しい。定期に試験がある。そのためにも覚えねばならぬ知識は膨大である。皆、昼夜を分かたず机に向った。
当初、同期の中で隼人の成績は群を抜いていた。酒を気付けにして、無茶な勉学。
「最初だけは意欲を亢進させるから、酒も」
「俺は誰にも負けん負ける気がせん、特にお前には、とかいってた」慎一郎が苦く笑った。
「尖ってむきになって。それが今じゃ―」
今の酒は勉学を助ける気付どころか、前途、いや命すら脅かす枷になってしまっている。
「このままじゃ―なんとかせんと」
「こいつ、もうかなりやられている。気付いているだろ?」
「ああ、夜中に目覚めるとな、隼人のやつ布団の上に起き上がって、ぶつぶつ一人でしゃべってるんだ」
「お前も知ってたか」
「まるでそこに話し相手がいるみたいに、いつまでも一人でつぶやいてなあ。まあ一過性の酔っ払いでも幻視幻聴相手にしたりすること、稀にはあるが―」
「いや、こいつはほんまもんだ。脳髄、酒に冒されかけてる。それなのに、飲まずにいられないのが、病か」慎一郎は、悲しげに隼人の寝姿を見た。
「だが、これ以上、俺達に何が出来るんだ」
ぶつける相手のない怒りが湧く。
「思いつくことはやってみたなあ」
止めろといって止めるものなら苦労はない。二人顔を見合わせ、吐息をつくしかない。
当初、同期の中で隼人の成績は群を抜いていた。酒を気付けにして、無茶な勉学。
「最初だけは意欲を亢進させるから、酒も」
「俺は誰にも負けん負ける気がせん、特にお前には、とかいってた」慎一郎が苦く笑った。
「尖ってむきになって。それが今じゃ―」
今の酒は勉学を助ける気付どころか、前途、いや命すら脅かす枷になってしまっている。
「このままじゃ―なんとかせんと」
「こいつ、もうかなりやられている。気付いているだろ?」
「ああ、夜中に目覚めるとな、隼人のやつ布団の上に起き上がって、ぶつぶつ一人でしゃべってるんだ」
「お前も知ってたか」
「まるでそこに話し相手がいるみたいに、いつまでも一人でつぶやいてなあ。まあ一過性の酔っ払いでも幻視幻聴相手にしたりすること、稀にはあるが―」
「いや、こいつはほんまもんだ。脳髄、酒に冒されかけてる。それなのに、飲まずにいられないのが、病か」慎一郎は、悲しげに隼人の寝姿を見た。
「だが、これ以上、俺達に何が出来るんだ」
ぶつける相手のない怒りが湧く。
「思いつくことはやってみたなあ」
止めろといって止めるものなら苦労はない。二人顔を見合わせ、吐息をつくしかない。
Posted by 渋柿 at 15:41 | Comments(0)
2009年06月06日
「伏見桃片伊万里」5
今までは塾生の多くが、郷里藩校等で一応医学を修めた医者だった。それが、時代ゆえか、医学を飛ばして直接洋学に飛び込む塾生も出はじめた。古参の弟子達も、語学や政治学・法学・軍事知識等の学問に目が向いている。当然、圭吾ら二十歳前後の塾生が主に治療所の診療当番に当ることになってしまった。
食事当番はまだしも輪番が保たれたているが、診療体制としては、兄弟子は一月に数回、深夜の宿直をこなす程度である。
この日、慎一郎が塾から帰ってきたのは、子の刻近く。急患があったという。竈はもちろん、唯一の暖である小火鉢の火種も、尽きている。米櫃の上に下げてきた風呂敷包を乗せ、冷めた雑炊をそのまま掻込んだ。
「何だ?」
「先生からお裾分け。梅干と、鰹節は到来ものらしい」
師夫妻は折に触れ、男所帯を心遣う。隼人は、酔いつぶれている。二階から掻巻きを持ってきてかけてやるのは圭吾の日課になってしまった。
「困ったものだ。先生も案じておられた」慎一郎は圭吾の顔を見た。
「こいつ、大阪へ来るまで、自分の口にしたことはなかったらしい、酒」
「ああ。こいつ臓腑が下手に丈夫過ぎるんだ。毎日毎日、普通の胃の腑じゃ、まずここまで飲めんよ。親が存命なら、泣くぞ」
「天涯孤独、幸か不幸かな。親を早く亡くして、こいつが継ぐはずだった家は叔父御が家督しちまったっていうし」
「まあ、叔父御に育てられ、お陰で医者になれて、今も仕送りは途切れんらしい」
叔父は二十石取りであったか、とてもゆとりある暮らしなどではない筈の中で、義理ある隼人に精一杯のことをしてくれている。
「隼人も、叔父御に義理があるな」
「叔父御にも息子が産れたってさ。国に帰りゃ、双方義理絡み、面倒も起こる。もう帰るに帰れん・・まあ、こいつも酒でも飲まなきゃやってられんか」
塾は塾生の飲酒を禁じているが、建前。手荒い新入歓迎は習いだ。圭吾や慎一郎は終日二日酔いに苦しんだのに、隼人だけはケロリとしていた。肝の臓の性が違うらしい。
食事当番はまだしも輪番が保たれたているが、診療体制としては、兄弟子は一月に数回、深夜の宿直をこなす程度である。
この日、慎一郎が塾から帰ってきたのは、子の刻近く。急患があったという。竈はもちろん、唯一の暖である小火鉢の火種も、尽きている。米櫃の上に下げてきた風呂敷包を乗せ、冷めた雑炊をそのまま掻込んだ。
「何だ?」
「先生からお裾分け。梅干と、鰹節は到来ものらしい」
師夫妻は折に触れ、男所帯を心遣う。隼人は、酔いつぶれている。二階から掻巻きを持ってきてかけてやるのは圭吾の日課になってしまった。
「困ったものだ。先生も案じておられた」慎一郎は圭吾の顔を見た。
「こいつ、大阪へ来るまで、自分の口にしたことはなかったらしい、酒」
「ああ。こいつ臓腑が下手に丈夫過ぎるんだ。毎日毎日、普通の胃の腑じゃ、まずここまで飲めんよ。親が存命なら、泣くぞ」
「天涯孤独、幸か不幸かな。親を早く亡くして、こいつが継ぐはずだった家は叔父御が家督しちまったっていうし」
「まあ、叔父御に育てられ、お陰で医者になれて、今も仕送りは途切れんらしい」
叔父は二十石取りであったか、とてもゆとりある暮らしなどではない筈の中で、義理ある隼人に精一杯のことをしてくれている。
「隼人も、叔父御に義理があるな」
「叔父御にも息子が産れたってさ。国に帰りゃ、双方義理絡み、面倒も起こる。もう帰るに帰れん・・まあ、こいつも酒でも飲まなきゃやってられんか」
塾は塾生の飲酒を禁じているが、建前。手荒い新入歓迎は習いだ。圭吾や慎一郎は終日二日酔いに苦しんだのに、隼人だけはケロリとしていた。肝の臓の性が違うらしい。
Posted by 渋柿 at 20:24 | Comments(0)
2009年06月06日
「伏見桃片伊万里」4
嘉永六年甲寅という。明治維新の十余年前ということになる。堀圭吾が大阪の医塾に学んで三年目の初春であった。大阪、堂島に程近い書過(かいしょ)町の蘭学塾。ここは、その当時でも上総佐倉の佐藤泰然の順天堂と並び賞される医塾であった。
この塾は、当初から塾生の住込みを原則としていた。圭吾が借家から通ったのは、例外である。肥前伊万里、陶器商の生家は、代々士分を金であがなっている。「鎖国」を布いていた佐賀藩領から、大阪遊学が認められたのもその故であった。但し経費の殆どは圭吾の父の負担ではあったが。父は、塾の近くの仕舞屋(しもたや)一軒丸々を借りてくれた。最初、圭吾は謝絶した。「ありがたく受けるがよい」とむしろ強く勧めたのは師である。「うちが塾生をこの狭い棟に住みこませているのは、皆が長屋など借りる余裕もないからじゃ。他意はない。暗く狭い場の方が学問が進むと言うわけもないじゃろ。ご生家に余裕があって仕舞屋を借りて貰えるなら、それにこしたことはないと思うが」師はそういった。
塾と同じ淀橋、歩いて四半刻とかからぬ近場に、圭吾の寝起きする仕舞屋がある。台所と土間に六畳二間、二階に六畳と四畳半と、一人住まいには贅沢なほどの塒であった。
七草の、縄暖簾の酒盛りの翌々日、正月の松も取れた九日の夕でのことである。
圭吾は塾の勉学と医療をすませ、朝炊いておいた飯を残りの味噌汁に入れて雑炊にして夕餉とした。日課であった。淀橋の塾生の、多くは下級武士階層の出で炊事は苦にならぬ。
ざっとは飯・汁も自分達で煮炊きした。木賃・米味噌塩に青物代などを折半し、当番で朝と夕餉を整えた。昼食は朝の残り。握飯の時もある。通いの圭吾は、昼だけを塾で摂る。
仕送りと、天満の叔父から貰う小遣い、圭吾の懐は暖かい身であるから、たまさかには、酒食も友に奢れる。そのうちの一人が酔って塾に帰らなく―いや帰れなくなった。圭吾の家に泊まることが重なり、あげく深夜泥酔して訪れ上がり込んだ。そのままずるずると居ついて、共同生活の羽目になってしまったのだ。人の良い圭吾も、立派な酒乱のその村田隼人は持て余した。師は、隼人が圭吾の塒に転がり込むことを黙認し、同時に同じく栗林慎一郎に圭吾や隼人とともに起居するように命じた。慎一郎は同年ながら、今や隼人や圭吾のお目付け役のような立場になっている。
この塾は、当初から塾生の住込みを原則としていた。圭吾が借家から通ったのは、例外である。肥前伊万里、陶器商の生家は、代々士分を金であがなっている。「鎖国」を布いていた佐賀藩領から、大阪遊学が認められたのもその故であった。但し経費の殆どは圭吾の父の負担ではあったが。父は、塾の近くの仕舞屋(しもたや)一軒丸々を借りてくれた。最初、圭吾は謝絶した。「ありがたく受けるがよい」とむしろ強く勧めたのは師である。「うちが塾生をこの狭い棟に住みこませているのは、皆が長屋など借りる余裕もないからじゃ。他意はない。暗く狭い場の方が学問が進むと言うわけもないじゃろ。ご生家に余裕があって仕舞屋を借りて貰えるなら、それにこしたことはないと思うが」師はそういった。
塾と同じ淀橋、歩いて四半刻とかからぬ近場に、圭吾の寝起きする仕舞屋がある。台所と土間に六畳二間、二階に六畳と四畳半と、一人住まいには贅沢なほどの塒であった。
七草の、縄暖簾の酒盛りの翌々日、正月の松も取れた九日の夕でのことである。
圭吾は塾の勉学と医療をすませ、朝炊いておいた飯を残りの味噌汁に入れて雑炊にして夕餉とした。日課であった。淀橋の塾生の、多くは下級武士階層の出で炊事は苦にならぬ。
ざっとは飯・汁も自分達で煮炊きした。木賃・米味噌塩に青物代などを折半し、当番で朝と夕餉を整えた。昼食は朝の残り。握飯の時もある。通いの圭吾は、昼だけを塾で摂る。
仕送りと、天満の叔父から貰う小遣い、圭吾の懐は暖かい身であるから、たまさかには、酒食も友に奢れる。そのうちの一人が酔って塾に帰らなく―いや帰れなくなった。圭吾の家に泊まることが重なり、あげく深夜泥酔して訪れ上がり込んだ。そのままずるずると居ついて、共同生活の羽目になってしまったのだ。人の良い圭吾も、立派な酒乱のその村田隼人は持て余した。師は、隼人が圭吾の塒に転がり込むことを黙認し、同時に同じく栗林慎一郎に圭吾や隼人とともに起居するように命じた。慎一郎は同年ながら、今や隼人や圭吾のお目付け役のような立場になっている。
Posted by 渋柿 at 07:59 | Comments(0)
2009年06月05日
「伏見桃片伊万里」3
親父は別に怒った風もなく、銚子と土瓶を置き、汚れた器を下げた。隼人が、また一杯を一気に呷る。
「何か食べろよ、胃の腑が荒れるぞ」
「放といてくれ」
「隼人」
「お前―」
「すまん、本当に喰えんのだ」
(こりゃあ―)
(ああ、洒落じゃ済まんぞ)
慎一郎と圭吾は瞳を交した。一人で飲むから酒量が増える、ならいっそ、と相談して今宵居酒屋へ誘った。だが結果は芳しくない。黙って茶を啜る。暮早い冬とはいえまだ宵の口、他の客はなかなか来なかった。
親父が、湯気の立つ碗を運んできた。
「これは?」
「七草粥でんがな。今日は若菜の節句、御禁裏(きんり)さまでもあがられまっせ」
「そうか、今日は七草か」
「口開けの、わしの驕り、気い悪うせんと食べてくだされ」
「それはすまん。ありがたく頂こう」
「粥なら喰えるだろ、隼人」
ああ、とはいったものの、結局隼人は小ぶりの碗の半分も食べられなかった。
遠く、蹄の音がした。この居酒屋に座を占めてから、これで三度目だろうか。往来をゆ
く早馬らしい。
「堂島の米相場か」
ここから淀川橋と中州を挟んで遠くもない地に、元禄元年に開設されたという堂島の米
穀取引所があった。「堂島の米相場」は先物取引の日本のみならず世界的先駆であった。
大名とその御用商人ら豪商が利害を或いは一致させ、或いは拮抗させつつ、大金が動き大金に動かされる場所である。
「つい先ごろ、丸に十の字さまが大相場を張られたそうですが」親爺が不安そうに言った。
「丸に―?薩摩の島津か」
「へえ。薩摩さまとか長州さまとか肥前さまとか―干拓やら新田開きで田んぼ広げはった藩が再々大相場を張られましてなあ。相場ん動きは早馬やら早飛脚で伝えまっしゃろ。馬に蹴られるお人が出ねばよろしゅうおすけどなあ。全く、物騒なこっちゃ」
刻々情勢が変わる米相場の通信には、烽火の中継まで使われたと記録にある。情報の一瞬の遅れが大損を招くリスクは、今日の相場と同じであった。
「年寄り子供は用心せねばならぬのう」
心配そうな慎一郎と圭吾を、隼人はどこか虚ろな目で見ている。
「何か食べろよ、胃の腑が荒れるぞ」
「放といてくれ」
「隼人」
「お前―」
「すまん、本当に喰えんのだ」
(こりゃあ―)
(ああ、洒落じゃ済まんぞ)
慎一郎と圭吾は瞳を交した。一人で飲むから酒量が増える、ならいっそ、と相談して今宵居酒屋へ誘った。だが結果は芳しくない。黙って茶を啜る。暮早い冬とはいえまだ宵の口、他の客はなかなか来なかった。
親父が、湯気の立つ碗を運んできた。
「これは?」
「七草粥でんがな。今日は若菜の節句、御禁裏(きんり)さまでもあがられまっせ」
「そうか、今日は七草か」
「口開けの、わしの驕り、気い悪うせんと食べてくだされ」
「それはすまん。ありがたく頂こう」
「粥なら喰えるだろ、隼人」
ああ、とはいったものの、結局隼人は小ぶりの碗の半分も食べられなかった。
遠く、蹄の音がした。この居酒屋に座を占めてから、これで三度目だろうか。往来をゆ
く早馬らしい。
「堂島の米相場か」
ここから淀川橋と中州を挟んで遠くもない地に、元禄元年に開設されたという堂島の米
穀取引所があった。「堂島の米相場」は先物取引の日本のみならず世界的先駆であった。
大名とその御用商人ら豪商が利害を或いは一致させ、或いは拮抗させつつ、大金が動き大金に動かされる場所である。
「つい先ごろ、丸に十の字さまが大相場を張られたそうですが」親爺が不安そうに言った。
「丸に―?薩摩の島津か」
「へえ。薩摩さまとか長州さまとか肥前さまとか―干拓やら新田開きで田んぼ広げはった藩が再々大相場を張られましてなあ。相場ん動きは早馬やら早飛脚で伝えまっしゃろ。馬に蹴られるお人が出ねばよろしゅうおすけどなあ。全く、物騒なこっちゃ」
刻々情勢が変わる米相場の通信には、烽火の中継まで使われたと記録にある。情報の一瞬の遅れが大損を招くリスクは、今日の相場と同じであった。
「年寄り子供は用心せねばならぬのう」
心配そうな慎一郎と圭吾を、隼人はどこか虚ろな目で見ている。
Posted by 渋柿 at 09:26 | Comments(0)
2009年06月04日
「伏見桃片伊万里」2
「その酒仙が、人は土から造られたんだって教えてくれたことがあってさ」
「耶蘇(やそ)か、そいつ」
そこは蘭方の医生である、御禁制の基督(きりすと)教とやらのこと齧(かじ)らぬでもないようだ。
「まさか。女媧だよ」
「女媧?何だそりゃ」
慎一郎はその字すら思い浮かばないらしい。
「女と書いてジョ、カは女偏にそう、渦って言う字の旁だ。過去の過の之繞のない奴な。女媧は神様ていうか、伝説の女神だなあ、大昔の唐土の」
今まで、黙って箸を動かしていた影の薄そうな男、堀圭吾が、話に加わった。
「確か黄帝・神農・女媧で三皇、あの三皇五帝の一人だった筈だ。黄河の土捏(こ)ねて、人を造ったとかいう神さ」
「そう、さすが圭吾は焼物屋の倅だ。この女神さんは、初めのうちは一つ一つ丁寧に土を丸めてたんが、飽きてきてな、揚句縄を泥水に突っ込んで振り回して、飛ばしを人間にしたんだな。だから人にゃ一握りの俊才と、大多数の暗凡のふた色いるんだってさ」
隼人は、三本目の銚子を手酌で傾けた。すでに空であった。舌打ちして振ると、数滴のしずくが垂れた。
「ちっ。親爺、もう一本頼む」
「おい、いい加減にしろ!」
慎一郎が、隼人をにらみつけた。
「今日は圭吾の奢りだろう。なっ。親父、もう一本だ。俺ぁ所詮泥水の裔よ。酒毒結構。おい圭吾、出来損ないん焼き物ってのは窯出しん時、割っちまうんだろ」
隼人は圭吾に向き直った。
「こっちには茶を、土瓶で頼む。―まあそいうことにはなってはいるんだが、出来は悪くたって一応、器は器だ。自分ところで使ったり隣近所が貰ったり、それなりに、さ。出来が悪いからってそう、むやみに割っちまうもんでもないんだ」
「そうか」
「そう、出来損ないだって、この世に生まれ出たからは役目を果したかろう。そこの―おっと!」
慎一郎が、言いかけて止めた。居酒屋の親父が、銚子と土瓶を持って苦笑している。
「はいな、うちとこの器は尾州の安もんどすわ。伊万里たらゆう窯元さんどしたら、日の目みんもん使わせてもろとります。・・でもまあ酒毒ん話肴(さかな)に酒とは、まったく酔狂なお医者はん達や」
親父は別に怒った風もなく、銚子と土瓶を置き、汚れた器を下げた。隼人が、また一杯を一気に呷る。
「耶蘇(やそ)か、そいつ」
そこは蘭方の医生である、御禁制の基督(きりすと)教とやらのこと齧(かじ)らぬでもないようだ。
「まさか。女媧だよ」
「女媧?何だそりゃ」
慎一郎はその字すら思い浮かばないらしい。
「女と書いてジョ、カは女偏にそう、渦って言う字の旁だ。過去の過の之繞のない奴な。女媧は神様ていうか、伝説の女神だなあ、大昔の唐土の」
今まで、黙って箸を動かしていた影の薄そうな男、堀圭吾が、話に加わった。
「確か黄帝・神農・女媧で三皇、あの三皇五帝の一人だった筈だ。黄河の土捏(こ)ねて、人を造ったとかいう神さ」
「そう、さすが圭吾は焼物屋の倅だ。この女神さんは、初めのうちは一つ一つ丁寧に土を丸めてたんが、飽きてきてな、揚句縄を泥水に突っ込んで振り回して、飛ばしを人間にしたんだな。だから人にゃ一握りの俊才と、大多数の暗凡のふた色いるんだってさ」
隼人は、三本目の銚子を手酌で傾けた。すでに空であった。舌打ちして振ると、数滴のしずくが垂れた。
「ちっ。親爺、もう一本頼む」
「おい、いい加減にしろ!」
慎一郎が、隼人をにらみつけた。
「今日は圭吾の奢りだろう。なっ。親父、もう一本だ。俺ぁ所詮泥水の裔よ。酒毒結構。おい圭吾、出来損ないん焼き物ってのは窯出しん時、割っちまうんだろ」
隼人は圭吾に向き直った。
「こっちには茶を、土瓶で頼む。―まあそいうことにはなってはいるんだが、出来は悪くたって一応、器は器だ。自分ところで使ったり隣近所が貰ったり、それなりに、さ。出来が悪いからってそう、むやみに割っちまうもんでもないんだ」
「そうか」
「そう、出来損ないだって、この世に生まれ出たからは役目を果したかろう。そこの―おっと!」
慎一郎が、言いかけて止めた。居酒屋の親父が、銚子と土瓶を持って苦笑している。
「はいな、うちとこの器は尾州の安もんどすわ。伊万里たらゆう窯元さんどしたら、日の目みんもん使わせてもろとります。・・でもまあ酒毒ん話肴(さかな)に酒とは、まったく酔狂なお医者はん達や」
親父は別に怒った風もなく、銚子と土瓶を置き、汚れた器を下げた。隼人が、また一杯を一気に呷る。
Posted by 渋柿 at 13:42 | Comments(0)
2009年06月03日
「伏見桃片伊万里」1
野良犬も冷え強(きつ)い川筋を避け、蹲(うずくま)って震えていた。突き刺さるような寒風が、鋭い音を立てて淀川べりから路地(ろじ)裏(うら)に吹き抜けた。まだ夕暮れ前という時刻である。
今日の商売を始めたばかりの筈の、揺れる赤提灯と縄暖簾のうちには、すでに客の酔声がしていた。それも、次第に大きくなる。
「そうさ。あれこそ、仙人だったんだ」
客の一人がそう言うと、一気に杯を干した。
「その来歴は全くわからん。とにかくどっからかやって来て、地蔵堂に寝起きしてさ。萩の城下の外れにな。なりは僧形(そうぎょう)だったな、一応。でも、本当の坊主だったかどうか。寺子屋みたいなことやってたけど、口にするのは仕舞にゃ殆ど酒でさ。酒仙(しゅせん)だなあ。揚句(あげく)にゃあ寺子は俺だけ」
縄暖簾がばたばたと鳴る。
居酒屋は狭く、小奇麗とは言い難い。壁に貼り付けてある煮しめやら焼魚やら品書の黄ばんだ紙も、何やら貧乏臭い。
紙の裏の糊は、どうやら飯粒らしい。
煮物焼物の香が混じって籠った店の中では、医者髷の若い男が三人、小半刻ほど前から入込で呑んでいた。先ほどからしきりにしゃべっている村田隼人は、その中の一人だった。 上背はあるが、痩せている。先ほどから酒でかなり饒舌である。
煤けた屏風の脇に置かれた、小火鉢の炭は、おき火になりかかけている。
「お前が長州は儀の話をするのはめずらしいがな、酒仙ちゅうより酒毒だ、そりゃ」
小柄で、医者髷が似合わぬ童顔の栗林慎一郎が答えた。先刻から、ろれつ怪しい隼人の相槌は専らこの男が勤めている。
「ああ。死んだよ。酒でな。よりによって真夏、俺が見つけたときゃ蝿がたかってて。腐臭、だったはずなんだが、酒精と交じり合って、何か芳しい香りがしてたよ。―多分極楽往生したんだろうぜ」
「お前、そのとき幾つだ」
「たしか七つだ。ませてたかな。そう、そのあとすぐ、親父が死んだんでな、間違いない。お袋が死んだのは翌年だった」
肴は餡(あん)かけ豆腐、鯖の塩焼き、風呂吹き大根などであった。隼人は、これらを殆ど口にしていない。ただ水のように杯を重ねている。
空の二合銚子が二本、そのうち三が二は隼人一人で飲んでしまっていた。
今日の商売を始めたばかりの筈の、揺れる赤提灯と縄暖簾のうちには、すでに客の酔声がしていた。それも、次第に大きくなる。
「そうさ。あれこそ、仙人だったんだ」
客の一人がそう言うと、一気に杯を干した。
「その来歴は全くわからん。とにかくどっからかやって来て、地蔵堂に寝起きしてさ。萩の城下の外れにな。なりは僧形(そうぎょう)だったな、一応。でも、本当の坊主だったかどうか。寺子屋みたいなことやってたけど、口にするのは仕舞にゃ殆ど酒でさ。酒仙(しゅせん)だなあ。揚句(あげく)にゃあ寺子は俺だけ」
縄暖簾がばたばたと鳴る。
居酒屋は狭く、小奇麗とは言い難い。壁に貼り付けてある煮しめやら焼魚やら品書の黄ばんだ紙も、何やら貧乏臭い。
紙の裏の糊は、どうやら飯粒らしい。
煮物焼物の香が混じって籠った店の中では、医者髷の若い男が三人、小半刻ほど前から入込で呑んでいた。先ほどからしきりにしゃべっている村田隼人は、その中の一人だった。 上背はあるが、痩せている。先ほどから酒でかなり饒舌である。
煤けた屏風の脇に置かれた、小火鉢の炭は、おき火になりかかけている。
「お前が長州は儀の話をするのはめずらしいがな、酒仙ちゅうより酒毒だ、そりゃ」
小柄で、医者髷が似合わぬ童顔の栗林慎一郎が答えた。先刻から、ろれつ怪しい隼人の相槌は専らこの男が勤めている。
「ああ。死んだよ。酒でな。よりによって真夏、俺が見つけたときゃ蝿がたかってて。腐臭、だったはずなんだが、酒精と交じり合って、何か芳しい香りがしてたよ。―多分極楽往生したんだろうぜ」
「お前、そのとき幾つだ」
「たしか七つだ。ませてたかな。そう、そのあとすぐ、親父が死んだんでな、間違いない。お袋が死んだのは翌年だった」
肴は餡(あん)かけ豆腐、鯖の塩焼き、風呂吹き大根などであった。隼人は、これらを殆ど口にしていない。ただ水のように杯を重ねている。
空の二合銚子が二本、そのうち三が二は隼人一人で飲んでしまっていた。
Posted by 渋柿 at 12:29 | Comments(2)