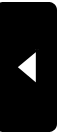2009年01月17日
「尾張享元絵巻」11
昨日も獲物が多かった。気分よく主従で杯を交わしていると、近習の千村(ちむら)親(しん)平(ぺい)が遠慮がちに茶室の縁の下にうずくまった。
「何か?」織部が尋ねる。
「伊吹屋が・・参っております」
「伊吹屋とな」
宗春も杯を置く。
「何かまた持って参ったか?」
「は、荷車にて千両箱を十」
一万両である。
「是非に、お殿さまにお目にかかりたいと申しておりますが・・」
「ふうむ・・」宗春はまた杯を含んだ。
「土産が土産じゃ。すげなくもできまい。これへ通せ」
「御深井の丸に・・商人・・?」
「伊吹屋とは、前にもここでおうたわ。かまわぬ、ここへ連れて参れ」
「はっ」
親平は応えて立ち上がった。
この夏の初対面の後、宗春は伊吹屋の過去を横目だけでなく、藩主直属の隠密にも更に詳しく調べさせている。
「奥州仙台城下で、薬種問屋の番頭をしておりました」
そう隠密の頭から報告を受けたのは、つい数日前であった。
「薬屋の番頭であったか」
そこから薬湯の無尽まがいを思いついたか、と宗春は笑った。
「詳しゅうは、この報告書に。元は浪人というは確かなようで。仙台一の大店蓬莱屋の主が商用で江戸に参りました折、掏られた財布を取り戻したのが今の伊吹屋だったとか。算勘に明るく機転が利きますもので主人はすっかり気に入り、仙台に連れ帰ったらしゅうございます」
「そこで、両刀を捨てたか」
「初めは蓬莱屋の客分というか居候のようにして厄介になっておったそうですが、自分から奉公したいと主人に頼んだそうで。それも小僧並でよいから商売を覚えさせてくれと」
「そこで商売を呑み込んで、尾張で一儲けしておるわけか」
「はい。仙台の蓬莱屋には今も盆暮れ便りを欠かしておりません」
「伊吹御神湯の商売の元手も、蓬莱屋の融通か?」
「いえ、仙台に参りましたものの調べでは、蓬莱屋は伊吹屋の商いのやり方は知らぬようで」
「ただの薬種問屋をやっていると思っているのだな」
「はい。いやしくも伊達陸奥守様ご城下一の大店が、騙りまがいに元手を降ろすとも思えませぬ」
「ということは、蓬莱屋の引き金(退職金)と、奉公中の蓄えを当てたのであろうのう」
「そう、思われます」
「ご苦労であった」
渡された報告書は、仙台での探索も含み、詳細であった。
「何か?」織部が尋ねる。
「伊吹屋が・・参っております」
「伊吹屋とな」
宗春も杯を置く。
「何かまた持って参ったか?」
「は、荷車にて千両箱を十」
一万両である。
「是非に、お殿さまにお目にかかりたいと申しておりますが・・」
「ふうむ・・」宗春はまた杯を含んだ。
「土産が土産じゃ。すげなくもできまい。これへ通せ」
「御深井の丸に・・商人・・?」
「伊吹屋とは、前にもここでおうたわ。かまわぬ、ここへ連れて参れ」
「はっ」
親平は応えて立ち上がった。
この夏の初対面の後、宗春は伊吹屋の過去を横目だけでなく、藩主直属の隠密にも更に詳しく調べさせている。
「奥州仙台城下で、薬種問屋の番頭をしておりました」
そう隠密の頭から報告を受けたのは、つい数日前であった。
「薬屋の番頭であったか」
そこから薬湯の無尽まがいを思いついたか、と宗春は笑った。
「詳しゅうは、この報告書に。元は浪人というは確かなようで。仙台一の大店蓬莱屋の主が商用で江戸に参りました折、掏られた財布を取り戻したのが今の伊吹屋だったとか。算勘に明るく機転が利きますもので主人はすっかり気に入り、仙台に連れ帰ったらしゅうございます」
「そこで、両刀を捨てたか」
「初めは蓬莱屋の客分というか居候のようにして厄介になっておったそうですが、自分から奉公したいと主人に頼んだそうで。それも小僧並でよいから商売を覚えさせてくれと」
「そこで商売を呑み込んで、尾張で一儲けしておるわけか」
「はい。仙台の蓬莱屋には今も盆暮れ便りを欠かしておりません」
「伊吹御神湯の商売の元手も、蓬莱屋の融通か?」
「いえ、仙台に参りましたものの調べでは、蓬莱屋は伊吹屋の商いのやり方は知らぬようで」
「ただの薬種問屋をやっていると思っているのだな」
「はい。いやしくも伊達陸奥守様ご城下一の大店が、騙りまがいに元手を降ろすとも思えませぬ」
「ということは、蓬莱屋の引き金(退職金)と、奉公中の蓄えを当てたのであろうのう」
「そう、思われます」
「ご苦労であった」
渡された報告書は、仙台での探索も含み、詳細であった。
Posted by 渋柿 at 16:48 | Comments(0)
2009年01月16日
「尾張享元絵巻」10
尾張徳川家の菩提寺建中(けんちゅう)寺への参詣の際も宗春は人々の度肝(どぎも)を抜く奇抜な衣装を着用した。行きは紅色(べにいろ)緋(ひ)縮緬(ちりめん)のくくり染めの装束に紅色の頭巾(ずきん)、帰りは白(しろ)練(ね)りの着物を着流し、帯は前結びにして二間(一間は一・八メートル)の長煙管(ながぎせる)の先を茶坊主に担がせ煙草の煙をくゆらせた。
名古屋城下は、この豪放な「殿さま」に拍手喝采した。
宗春は、自分自身の遊興だけに寛大であったのではない。
遊女町も、願い出る者があれば全て許可した。
家中の士の廓通(くるわがよ)いも黙認した。
歌舞伎・芝居の興行も、積極的に勧めた。
将軍の緊縮政策によって火の消えたようになっていた中で、名古屋だけがあかあかと灯(ひ)がともったようであった。そのことがどんなに吉宗を刺激していたか・・。
江戸時代、幕府体制そのものを維持しようとする「改革者」と、一藩、一都市の治安、繁栄をねがう地域行政官との対立は宿命である。
吉宗を始とする江戸後期以降の改革者たちの最終的な狙(ねら)いは、江戸をはじめとする主要都市の衰亡であった。都市が繁栄し、多くの消費人口を抱える力を持つ以上、農民は田畑を離れて都市に吸い寄せられ、農村が衰亡する。幕府経済の根本を農村が生産する米をはじめとした農産物に置いている以上、幕府の財政の建て直しとは、農村人口の維持増加であり、そのためには都市を衰亡させねばならないのである。
とまれ享保十六年の夏秋、宗春の治政下の名古屋は空前の繁栄であった。
秋、十月。深井の森は、楓(かえで)、錦(にしき)木(ぎ)、蔦(つた)、漆(うるし)で真っ赤に染まっている。昼下がり、時折の風に紅葉が池の水面に散り、鮮やかな模様を創る。
この日、宗春は気に入りの星野織部に相手をさせ、昼酒をたしなんでいた。
鶉(うずら)のつくね、炙(あぶ)った猪肉、兎肉は昨日織部らと行なった鷹狩の獲物である。
余談。
まさか鷹を使って猪は取れぬ。戦乱が絶えたこの時代の鷹狩である。鷹も勿論(もちろん)用いはするが、大名等の鷹狩には、槍、鉄砲も使う軍事演習という側面もあった。その証左、当時鷹狩の別名を鉄砲殺生と称した。
吉宗と宗春の共通点には、卑母所生(ひぼしょせい)の末子という他に、鷹狩を大いに好んだということもある。
生母の出自は、宿命的に二人の立場を峻別(しゅんべつ)している。
しかし、遠祖家康は、最晩年まで鷹狩を好んだという。
鷹狩りの点において、二人は等しく、家康の血を濃く受け継いだもの同士でもあった。
名古屋城下は、この豪放な「殿さま」に拍手喝采した。
宗春は、自分自身の遊興だけに寛大であったのではない。
遊女町も、願い出る者があれば全て許可した。
家中の士の廓通(くるわがよ)いも黙認した。
歌舞伎・芝居の興行も、積極的に勧めた。
将軍の緊縮政策によって火の消えたようになっていた中で、名古屋だけがあかあかと灯(ひ)がともったようであった。そのことがどんなに吉宗を刺激していたか・・。
江戸時代、幕府体制そのものを維持しようとする「改革者」と、一藩、一都市の治安、繁栄をねがう地域行政官との対立は宿命である。
吉宗を始とする江戸後期以降の改革者たちの最終的な狙(ねら)いは、江戸をはじめとする主要都市の衰亡であった。都市が繁栄し、多くの消費人口を抱える力を持つ以上、農民は田畑を離れて都市に吸い寄せられ、農村が衰亡する。幕府経済の根本を農村が生産する米をはじめとした農産物に置いている以上、幕府の財政の建て直しとは、農村人口の維持増加であり、そのためには都市を衰亡させねばならないのである。
とまれ享保十六年の夏秋、宗春の治政下の名古屋は空前の繁栄であった。
秋、十月。深井の森は、楓(かえで)、錦(にしき)木(ぎ)、蔦(つた)、漆(うるし)で真っ赤に染まっている。昼下がり、時折の風に紅葉が池の水面に散り、鮮やかな模様を創る。
この日、宗春は気に入りの星野織部に相手をさせ、昼酒をたしなんでいた。
鶉(うずら)のつくね、炙(あぶ)った猪肉、兎肉は昨日織部らと行なった鷹狩の獲物である。
余談。
まさか鷹を使って猪は取れぬ。戦乱が絶えたこの時代の鷹狩である。鷹も勿論(もちろん)用いはするが、大名等の鷹狩には、槍、鉄砲も使う軍事演習という側面もあった。その証左、当時鷹狩の別名を鉄砲殺生と称した。
吉宗と宗春の共通点には、卑母所生(ひぼしょせい)の末子という他に、鷹狩を大いに好んだということもある。
生母の出自は、宿命的に二人の立場を峻別(しゅんべつ)している。
しかし、遠祖家康は、最晩年まで鷹狩を好んだという。
鷹狩りの点において、二人は等しく、家康の血を濃く受け継いだもの同士でもあった。
Posted by 渋柿 at 16:34 | Comments(0)
2009年01月16日
連載「尾張享元絵巻」9
御深井の丸から戻ると、宗春は姫のため停止(ちょうじ)された祭りを行なうよう、改めて触れを出した。八月二十二日から二十三日の一昼夜、町中の踊り組二百あまりを次々に城内に呼んで踊らせて見物し、褒美の金を与えた。その金の出所は、実は伊吹屋である。茶室を辞するとき伊吹屋は、
「ほんの手土産(てみやげ)をお小姓の方にお預けしております」
といって帰っていった。
小姓の星野(ほしの)織部(おりべ)が困惑した表情で宗春の傍らに寄り、告げた。
「千両箱を五つ・・置いてまいりました・・」
「貰うておけ。きゃつの儲けのほんの一部であろう。下々の喜びのために遣おうよ」
宗春はさらりと言ってのけた。
(伊吹屋の身元、いま少し詳しく調べさせた方がよさそうじゃな)
自分の施策が、質素倹約によって揺らぎかけた幕府をたて直そうとしている将軍吉宗といずれ鋭く対立することを、まだ宗春は気付いていない。
宗春は藩主の座に就(つ)くにあたって「温知政要」という書を著(あら)わし、藩士たちに配った。
藩士たちを訓戒する、という形をとっているが、自分がどのような姿勢、政治方針で藩政に望むか一種のマニュフェストといてもよい。平易な文章に、宗春の面目が躍如。
曰(いわ)く、
「自分の好みを、人に押し付けるな。人にはそれぞれの好みがあるを認めるを、仁(じん)という」
従来、この「温知政要」は質素倹約一点張りの吉宗への皮肉と批判の書とされてきた。
筆者は、その解釈をとらぬ。
宗春も吉宗も生母の出自は低い。が、吉宗の母は農民の娘、宗春の母は商家の娘という違いがあった。
原則自給自足、倹約が最上の美徳の農民と違い、商人(あきんど)は他者の活発な消費がなければ成り立たぬ。人格形成に大きく影響するのは、やはり母親の存在であろう。商人は行政の規制を好まぬ。人々が倹約して消耗品を長く使い続けるとしたら、商品は動かず商売は「あがったり」である。重箱の隅をつつくように介入することは「かえつて下の痛み」。
もう一つ、肥沃(ひよく)な濃尾(のうび)平野を抱え、吉宗の産まれた紀州よりずっと「もの成り」の豊かな尾張の人々は、身分の上下を問わず「質素倹約」といわれても、ぴんと来なかったというのが実情であろう。なにしろ三十袋銀一枚の「伊吹御神湯」が伊吹屋の連鎖販売商法にもかかわらず十年売れ続けた土地である。
紀州は、尾張ほど富んではいない。
財政は、一時期、最悪であった。渋る幕府に頼み込み、借金までした。
吉宗の兄綱紀(つなのり)は、五代将軍綱(つな)吉(よし)の唯一の子女鶴姫を娶(めと)ったため、一時は六代将軍の候補に擬されもした。だが、そのため莫大な交際費が要った。
火災で藩邸の新築、鶴姫、綱紀、隠居の光貞、次兄の頼(より)職(よし)と続いた不幸のための葬儀の費用、藩財政の圧迫。吉宗が紀州藩主となったとき財政は破産寸前となっていた。それを吉宗は徹底した質素倹約で切り抜け、名君の誉(ほま)れをもって将軍の座に就いた。
商人の側の宗春の発想と、農民の出の母を持つ吉宗のそれとが、相(あい)容(いれ)ぬものであったのは必然であろう。
「ほんの手土産(てみやげ)をお小姓の方にお預けしております」
といって帰っていった。
小姓の星野(ほしの)織部(おりべ)が困惑した表情で宗春の傍らに寄り、告げた。
「千両箱を五つ・・置いてまいりました・・」
「貰うておけ。きゃつの儲けのほんの一部であろう。下々の喜びのために遣おうよ」
宗春はさらりと言ってのけた。
(伊吹屋の身元、いま少し詳しく調べさせた方がよさそうじゃな)
自分の施策が、質素倹約によって揺らぎかけた幕府をたて直そうとしている将軍吉宗といずれ鋭く対立することを、まだ宗春は気付いていない。
宗春は藩主の座に就(つ)くにあたって「温知政要」という書を著(あら)わし、藩士たちに配った。
藩士たちを訓戒する、という形をとっているが、自分がどのような姿勢、政治方針で藩政に望むか一種のマニュフェストといてもよい。平易な文章に、宗春の面目が躍如。
曰(いわ)く、
「自分の好みを、人に押し付けるな。人にはそれぞれの好みがあるを認めるを、仁(じん)という」
従来、この「温知政要」は質素倹約一点張りの吉宗への皮肉と批判の書とされてきた。
筆者は、その解釈をとらぬ。
宗春も吉宗も生母の出自は低い。が、吉宗の母は農民の娘、宗春の母は商家の娘という違いがあった。
原則自給自足、倹約が最上の美徳の農民と違い、商人(あきんど)は他者の活発な消費がなければ成り立たぬ。人格形成に大きく影響するのは、やはり母親の存在であろう。商人は行政の規制を好まぬ。人々が倹約して消耗品を長く使い続けるとしたら、商品は動かず商売は「あがったり」である。重箱の隅をつつくように介入することは「かえつて下の痛み」。
もう一つ、肥沃(ひよく)な濃尾(のうび)平野を抱え、吉宗の産まれた紀州よりずっと「もの成り」の豊かな尾張の人々は、身分の上下を問わず「質素倹約」といわれても、ぴんと来なかったというのが実情であろう。なにしろ三十袋銀一枚の「伊吹御神湯」が伊吹屋の連鎖販売商法にもかかわらず十年売れ続けた土地である。
紀州は、尾張ほど富んではいない。
財政は、一時期、最悪であった。渋る幕府に頼み込み、借金までした。
吉宗の兄綱紀(つなのり)は、五代将軍綱(つな)吉(よし)の唯一の子女鶴姫を娶(めと)ったため、一時は六代将軍の候補に擬されもした。だが、そのため莫大な交際費が要った。
火災で藩邸の新築、鶴姫、綱紀、隠居の光貞、次兄の頼(より)職(よし)と続いた不幸のための葬儀の費用、藩財政の圧迫。吉宗が紀州藩主となったとき財政は破産寸前となっていた。それを吉宗は徹底した質素倹約で切り抜け、名君の誉(ほま)れをもって将軍の座に就いた。
商人の側の宗春の発想と、農民の出の母を持つ吉宗のそれとが、相(あい)容(いれ)ぬものであったのは必然であろう。
Posted by 渋柿 at 06:57 | Comments(0)
2009年01月15日
腰岳の黒曜石の名を全国区に
【去年の佐賀新聞寄稿です】
「平沢(ひらぞう)良(ら)遺跡」伊万里市二里町川東 昭和40年代の土地開発で消滅

昭和36年、佐賀県や伊万里市の協力を受けた明治大学考古学研究室の杉原荘介教授らは、伊万里市の腰岳北西山麓で、旧石器遺跡の発掘調査を行いました。
腰岳の黒曜石は不純物が少なく、石端に衝撃を加えるとよく切れる刃物に似た剥片ができます。この発掘で剥片を剥がし取った痕跡を持つ石核が多数と、石(せき)匙(ひ)・石刃(せきじん)・石(せき)槍(そう)・鏃(やじり)包丁などの約200個の旧石器が出土し、石器製作工場の存在を示唆するものとされました。
杉原教授により、発掘場所は「平沢(ひらぞう)良(ら)遺跡」、特徴的な出土石核は「平沢良型石核」と命名されました。こうして伊万里・腰岳」の名前は旧石器遺跡として、「約1~2万年前の九州における最も古い人間の文化の一つが分った」という杉原教授の談話と共に全国区となったのです。
日本における旧石器時代は、長い間その存在すら疑問視されてました。昭和21年、無名の青年相沢忠弘さんの群馬県岩宿での発見により研究の固い扉は開かれます。相沢青年から連絡を受けて発掘に当たったのも杉原教授ら明治大学考古学研究室でした。翌々年日本の旧石器の存在が確認され、岩宿遺跡は今も保存されて、出土品は岩宿博物館に展示されています。
発掘から半世紀の時が流れました。有田川畔国道202号線と松浦鉄道が交差する地点のはずの「平沢良遺跡」は、近接する古墳時代の遺跡「椋露寺古墳」と共に、昭和40年代の土地開発により消滅しました。出土品の一部は伊万里歴史民俗資料館に収蔵されていますが、現在地図を頼りに訪れても、古代の人々の生活は腰岳の山容に偲ぶしかないのが残念です。
「平沢(ひらぞう)良(ら)遺跡」伊万里市二里町川東 昭和40年代の土地開発で消滅

昭和36年、佐賀県や伊万里市の協力を受けた明治大学考古学研究室の杉原荘介教授らは、伊万里市の腰岳北西山麓で、旧石器遺跡の発掘調査を行いました。
腰岳の黒曜石は不純物が少なく、石端に衝撃を加えるとよく切れる刃物に似た剥片ができます。この発掘で剥片を剥がし取った痕跡を持つ石核が多数と、石(せき)匙(ひ)・石刃(せきじん)・石(せき)槍(そう)・鏃(やじり)包丁などの約200個の旧石器が出土し、石器製作工場の存在を示唆するものとされました。
杉原教授により、発掘場所は「平沢(ひらぞう)良(ら)遺跡」、特徴的な出土石核は「平沢良型石核」と命名されました。こうして伊万里・腰岳」の名前は旧石器遺跡として、「約1~2万年前の九州における最も古い人間の文化の一つが分った」という杉原教授の談話と共に全国区となったのです。
日本における旧石器時代は、長い間その存在すら疑問視されてました。昭和21年、無名の青年相沢忠弘さんの群馬県岩宿での発見により研究の固い扉は開かれます。相沢青年から連絡を受けて発掘に当たったのも杉原教授ら明治大学考古学研究室でした。翌々年日本の旧石器の存在が確認され、岩宿遺跡は今も保存されて、出土品は岩宿博物館に展示されています。
発掘から半世紀の時が流れました。有田川畔国道202号線と松浦鉄道が交差する地点のはずの「平沢良遺跡」は、近接する古墳時代の遺跡「椋露寺古墳」と共に、昭和40年代の土地開発により消滅しました。出土品の一部は伊万里歴史民俗資料館に収蔵されていますが、現在地図を頼りに訪れても、古代の人々の生活は腰岳の山容に偲ぶしかないのが残念です。
Posted by 渋柿 at 11:00 | Comments(2)
2009年01月15日
連載「尾張享元絵巻」8
「そこで、行き倒れたち世話をいたすのか」
「はい、弱っておれば重湯(おもゆ)から粥(かゆ)を与え、医薬がいるなら手配し、若く仕事のできる者には、働き先の世話もいたします」
「では、年寄や病弱なものはどういたす」
「報謝宿の掃除、洗濯、病人の看病・・それに蓬摘みなど」
「蓬摘み?」
「先ほど申しましたように、報謝宿のかかりが、すべて伊吹屋から出ているのは伏せております。ですから宿ごとに、ここでは蓬を摘み、ここでは柚子の皮をむき、ここでは杉や松の葉を集め・・と別々の仕事を、してもらっております。晒しの小袋をたくさん縫ってもらうのも、乾かしたもろもろを刻んでもらうのも別々の宿の仕事・・」
「袋詰めだけが伊吹屋の奉公人の仕事か」
「はい。仕入れも小売もお客さまがやってくださいますので病人や捨て子も養える道理」
「こやつ・・」
宗春は破願した。
「尾張の太守として、民のために報謝宿を設けてくれたことは、篤(あつ)く、礼を申す。じゃがこののちも、講の隅々まで押し売りだけは出ぬように気を配れよ」
「この伊吹屋、このままこの商いをしても宜(よろ)しいので?」
「病気平癒の、紙きれ板切れで作ったお札でさえ、双方納得ずくで売り買いして、お上にとがめられた寺社はあるまい。この十年、だまされたとの訴えが一件もなかったのは、その方のやり方が民に受け入れられておるということじゃ」
「ありがとうございます」
伊吹屋は、形を改めて一礼した。
「殿さまは噂に違わぬ、まこと名君にあらせられます」
「世辞はよいと申しておろう。・・人は、病で、死ぬときは死ぬものよ。よほどの、悟り澄ました大徳、大知識か、よほどの阿呆(あほう)でもなければ、最後の最後まで何かにすがりたかろうよ」
伊吹屋はしばらく、涼しげなギヤマンの夏茶碗を見ていた。池を吹き渡ってくる風が涼しい。紅白の蓮の花が、重たげに揺れる。
「殿さまには、このたびのお姫さまのご不幸誠にご愁傷さまにて」
「三つまでの命の定めであったのよ」
宗春も寂しげに笑う。宗春の長女八百(やお)姫は、六月末、尾張藩江戸屋敷で死去していた。
「喪中とて、盆の踊りを楽しみにしていた下々に、気の毒なことであった・・」
「三つと申さば、手踊りなどお喜びの頃でございますなあ」
「ふむ」
宗春は伊吹屋の喫した夏茶碗をすすぎ、自服の茶を立てる。
夏たけて、もう不如帰の声はしない。未練気の老鶯が絶え絶え、鳴く。蝉時雨。ぽちゃん、池で鯉が跳ねた。
「今日にも、触れを出そう」
「はっ?」
「折角の年に一度の楽しみを奪っては気の毒じゃ。にぎやかな踊りは、姫にも何よりの供養・・そうじゃな、この二十四日から来月一日まで、盆踊りを勧めよう」
「それは何よりの姫さまへのご供養かと」
「八朔(はっさく)は徳川家には吉日でもある」
「はっ」
徳川家康が小田原(おだわら)の北条(ほうじょう)氏滅亡の後、住みなれた駿河(するが)、遠州(えんしゅう)、三河(みかわ)の地を離れて、はじめて江戸城に入城したのが八月一日、八朔は幕府の重要な行事、盛大に祝う。
「はい、弱っておれば重湯(おもゆ)から粥(かゆ)を与え、医薬がいるなら手配し、若く仕事のできる者には、働き先の世話もいたします」
「では、年寄や病弱なものはどういたす」
「報謝宿の掃除、洗濯、病人の看病・・それに蓬摘みなど」
「蓬摘み?」
「先ほど申しましたように、報謝宿のかかりが、すべて伊吹屋から出ているのは伏せております。ですから宿ごとに、ここでは蓬を摘み、ここでは柚子の皮をむき、ここでは杉や松の葉を集め・・と別々の仕事を、してもらっております。晒しの小袋をたくさん縫ってもらうのも、乾かしたもろもろを刻んでもらうのも別々の宿の仕事・・」
「袋詰めだけが伊吹屋の奉公人の仕事か」
「はい。仕入れも小売もお客さまがやってくださいますので病人や捨て子も養える道理」
「こやつ・・」
宗春は破願した。
「尾張の太守として、民のために報謝宿を設けてくれたことは、篤(あつ)く、礼を申す。じゃがこののちも、講の隅々まで押し売りだけは出ぬように気を配れよ」
「この伊吹屋、このままこの商いをしても宜(よろ)しいので?」
「病気平癒の、紙きれ板切れで作ったお札でさえ、双方納得ずくで売り買いして、お上にとがめられた寺社はあるまい。この十年、だまされたとの訴えが一件もなかったのは、その方のやり方が民に受け入れられておるということじゃ」
「ありがとうございます」
伊吹屋は、形を改めて一礼した。
「殿さまは噂に違わぬ、まこと名君にあらせられます」
「世辞はよいと申しておろう。・・人は、病で、死ぬときは死ぬものよ。よほどの、悟り澄ました大徳、大知識か、よほどの阿呆(あほう)でもなければ、最後の最後まで何かにすがりたかろうよ」
伊吹屋はしばらく、涼しげなギヤマンの夏茶碗を見ていた。池を吹き渡ってくる風が涼しい。紅白の蓮の花が、重たげに揺れる。
「殿さまには、このたびのお姫さまのご不幸誠にご愁傷さまにて」
「三つまでの命の定めであったのよ」
宗春も寂しげに笑う。宗春の長女八百(やお)姫は、六月末、尾張藩江戸屋敷で死去していた。
「喪中とて、盆の踊りを楽しみにしていた下々に、気の毒なことであった・・」
「三つと申さば、手踊りなどお喜びの頃でございますなあ」
「ふむ」
宗春は伊吹屋の喫した夏茶碗をすすぎ、自服の茶を立てる。
夏たけて、もう不如帰の声はしない。未練気の老鶯が絶え絶え、鳴く。蝉時雨。ぽちゃん、池で鯉が跳ねた。
「今日にも、触れを出そう」
「はっ?」
「折角の年に一度の楽しみを奪っては気の毒じゃ。にぎやかな踊りは、姫にも何よりの供養・・そうじゃな、この二十四日から来月一日まで、盆踊りを勧めよう」
「それは何よりの姫さまへのご供養かと」
「八朔(はっさく)は徳川家には吉日でもある」
「はっ」
徳川家康が小田原(おだわら)の北条(ほうじょう)氏滅亡の後、住みなれた駿河(するが)、遠州(えんしゅう)、三河(みかわ)の地を離れて、はじめて江戸城に入城したのが八月一日、八朔は幕府の重要な行事、盛大に祝う。
Posted by 渋柿 at 07:33 | Comments(0)
2009年01月14日
連載「尾張享元絵巻」7
「ときに、伊吹屋、ずいぶんと儲けたであろうな」
宗春は単刀直入に尋ねた。
「はっ、恐れ入ってございます」
言葉のわりに伊吹屋の顔色に変化はない。
「いかほど、儲けた?」
「さあて・・」
販売にかかる人件費はほとんどなく、原価もただ同然とすれば、儲けは莫大なものであろう。
「まこと伊吹御神湯とは万病を癒(いや)す効用があるものか?」
意地の悪い宗春の問いに動ぜず、伊吹屋は静かに茶を喫する。
「その前にそなた、伊吹山にて二十年の山籠りをいたしたのか?」
宗春は問いを重ねた。
「何によらず、万病を避けるという薬やら信心やらに金をかける者は、そもそも無茶をいたしませぬ」
伊吹屋落ち着き払っての答えは、宗春の後の問いを無視していた。
(やはり、山籠りは張ったりか)
商いのやり方がやり方である。それ位の大風呂敷は広げるであろう。
(そうであろうなあ)
「無茶、とは?」
宗春も、息吹屋の答えにのみ、問いを重ねる。
「一月銀一枚の湯に浸かって、深酒や大食いをいたしましょうか。これだけの元を払っておるのだから、と並みのものより日々摂生(せっせい)いたしましょう」
「ほう」
「鰯(いわし)の頭もなんとやら、病は気からというもあながち嘘ではございません。これで治ると思い込んで湯に浸かり本復する者も確かにございましょう。また、子供の喘息など時期がくれば自然に治る病気も多くございます」
「・・もしおぬしが死病に取りつかれたら、いかがいたす。御神湯に浸かるか?」
「いえ、腕のよい医者を捜しまする」
「ぷっ」
あまりの正直な答えであった。
「して儲けは。金は、そのまま蓄えておるのか?」
「いえ、報謝(ほうしゃ)宿(やど)に注ぎ込みました」
「報謝宿。あれは、そちが設けたものであったか」
尾張の長(おさ)として、行倒れや身寄りのない病人、捨て子のための今でいう私設福祉施設
「報謝宿」がいくつも東海道沿いに設けられたことは知っていた。悪(あ)しきことではないので、さしたる探索は命じていない。
「ご存知の通り、尾張は江戸から伊勢(いせ)参り、京、大坂への、旅人の通り道になっております。旅の途中病気になるもの、路銀が尽きて飢えるもの、また捨て子、年寄が大勢難渋しております」
「うーむ」
「そこで街道のあちこちに、そのような者を泊め、介抱し、場合によっては働き口を世話する報謝宿を―そう、この春で七つ目でしたか、開きました」
「伊吹屋の名をもってか?」
「いいえ学のある方など、手前の商法を毛嫌いなさいます。ご幼少の頃から御聡明と名高いお殿様が去年太守になられたとうかがい、てっきり手前の商(あきな)いは愚(おろ)か、この首もなきものと覚悟いたしました」
御定書百箇条によれば、偽薬を売った者は、引き回しの上、死罪、と定められている。
「世辞はよい」
「報謝宿に世話になっておるものは、賄(まかな)う金がこの伊吹屋から出たとは夢にも知らぬ筈(はず)でございます。そのように取り計らいました」
「そなた・・」まことの前身は何じゃ、という問いが喉元まで出掛かった。
宗春は単刀直入に尋ねた。
「はっ、恐れ入ってございます」
言葉のわりに伊吹屋の顔色に変化はない。
「いかほど、儲けた?」
「さあて・・」
販売にかかる人件費はほとんどなく、原価もただ同然とすれば、儲けは莫大なものであろう。
「まこと伊吹御神湯とは万病を癒(いや)す効用があるものか?」
意地の悪い宗春の問いに動ぜず、伊吹屋は静かに茶を喫する。
「その前にそなた、伊吹山にて二十年の山籠りをいたしたのか?」
宗春は問いを重ねた。
「何によらず、万病を避けるという薬やら信心やらに金をかける者は、そもそも無茶をいたしませぬ」
伊吹屋落ち着き払っての答えは、宗春の後の問いを無視していた。
(やはり、山籠りは張ったりか)
商いのやり方がやり方である。それ位の大風呂敷は広げるであろう。
(そうであろうなあ)
「無茶、とは?」
宗春も、息吹屋の答えにのみ、問いを重ねる。
「一月銀一枚の湯に浸かって、深酒や大食いをいたしましょうか。これだけの元を払っておるのだから、と並みのものより日々摂生(せっせい)いたしましょう」
「ほう」
「鰯(いわし)の頭もなんとやら、病は気からというもあながち嘘ではございません。これで治ると思い込んで湯に浸かり本復する者も確かにございましょう。また、子供の喘息など時期がくれば自然に治る病気も多くございます」
「・・もしおぬしが死病に取りつかれたら、いかがいたす。御神湯に浸かるか?」
「いえ、腕のよい医者を捜しまする」
「ぷっ」
あまりの正直な答えであった。
「して儲けは。金は、そのまま蓄えておるのか?」
「いえ、報謝(ほうしゃ)宿(やど)に注ぎ込みました」
「報謝宿。あれは、そちが設けたものであったか」
尾張の長(おさ)として、行倒れや身寄りのない病人、捨て子のための今でいう私設福祉施設
「報謝宿」がいくつも東海道沿いに設けられたことは知っていた。悪(あ)しきことではないので、さしたる探索は命じていない。
「ご存知の通り、尾張は江戸から伊勢(いせ)参り、京、大坂への、旅人の通り道になっております。旅の途中病気になるもの、路銀が尽きて飢えるもの、また捨て子、年寄が大勢難渋しております」
「うーむ」
「そこで街道のあちこちに、そのような者を泊め、介抱し、場合によっては働き口を世話する報謝宿を―そう、この春で七つ目でしたか、開きました」
「伊吹屋の名をもってか?」
「いいえ学のある方など、手前の商法を毛嫌いなさいます。ご幼少の頃から御聡明と名高いお殿様が去年太守になられたとうかがい、てっきり手前の商(あきな)いは愚(おろ)か、この首もなきものと覚悟いたしました」
御定書百箇条によれば、偽薬を売った者は、引き回しの上、死罪、と定められている。
「世辞はよい」
「報謝宿に世話になっておるものは、賄(まかな)う金がこの伊吹屋から出たとは夢にも知らぬ筈(はず)でございます。そのように取り計らいました」
「そなた・・」まことの前身は何じゃ、という問いが喉元まで出掛かった。
Posted by 渋柿 at 16:20 | Comments(0)
2009年01月14日
連載「尾張享元絵巻」6
「そうじゃの、折あらば躬(み)も直々(じきじき)に伊吹屋茂平と話してみたいものよ」
「な、なんと仰(おお)せられます」
「十年、破綻もせずにその商法の綱を渡ってまいったとすれば、さぞかし溜め込んでおろう。少々躬に融通してくれるやも知れぬ」
「殿お戯(たわむ)れを。騙りの上前をはねられるとは」
「戯れではない。日時はそちに任せるゆえ、伊吹屋を連れて参れ」
「捕らえるのではなく・・」
「客として招くのよ」
「―はっ」
付家老も太守の鶴の一声には逆らえぬ。
このことに限らず、宗春は竹越の杞憂(きゆう)を来たす命令を、既に多く発している。
宗春は、祭礼や祝いごとの規模を制限する倹約令を廃し、また武士の芝居見物の禁令を解いた。楽しみを与えるが藩主の務(つと)めと考えたゆえのことである。
夏の盛り。
御深井の丸は、名古屋城の北面に広がる、原生林を取りこんだ一郭である。
尾張初代藩主となる九男義(よし)直(なお)のために名古屋城を築いたとき、家康は城の北面に広がる湿地帯を「いざという時の逃げ場に」と教えた。
義直はその言葉を守り、湿地の中央の沼を掘り広げて東西三丁(一丁は一〇八メートル)、南北二丁の大池とし、南岸に小島築き、湿地を乾かした。岸辺にはあずまやや茶屋を設け、外からは判らぬように危急の際の退避、逃亡や立てこもりに必要な設備を施した。深井の森という原生林の中にも、密かに逃げ道を造った。一見、城主の風流のための一郭のように見えて、その実、城の秘密の中枢なのである。
御深井の丸には、何人(なんびと)も藩主の許可なく立ち入れぬ。
その日、宗春はみずから亭主となって、池端の茶屋の一つにしつらいをし、伊吹屋を朝茶に招いた。今日も暑くなるのだろう、深井の森の蝉(せみ)時雨(しぐれ)がはや、かしましい。障子は開け放してあるので一面の蓮(はす)の花が見渡せる。
茶室のにじり口があいた。やせた老人が、作法どおり狭い入り口を潜り抜け、客の座まで膝行(しっこう)した。
「お招き、ありがとうございます」
白扇を畳の縁外に置き、一揖(いちゆう)するのも作法にかなう。
(武士の出、というは確かなようじゃ)
宗春は風炉の釜にギヤマンの水差しから柄杓(ひしゃく)で数杯の水を差した。
水差しの蓋は、今朝宗春自身が、池で摘んだ緑鮮やかな蓮の葉である。床に活けてあるのも純白の蓮一輪。まだ開く前の蕾(つぼみ)である。
広口の、これもギヤマン造の夏茶碗に薄茶を立てた。蝉時雨が一段と高まる。息吹屋は自身膝行して碗をわが座に取り入れた。
「頂戴いたします」また一揖。
伊吹屋茂平は茶の心得並々ならぬと見える。
「な、なんと仰(おお)せられます」
「十年、破綻もせずにその商法の綱を渡ってまいったとすれば、さぞかし溜め込んでおろう。少々躬に融通してくれるやも知れぬ」
「殿お戯(たわむ)れを。騙りの上前をはねられるとは」
「戯れではない。日時はそちに任せるゆえ、伊吹屋を連れて参れ」
「捕らえるのではなく・・」
「客として招くのよ」
「―はっ」
付家老も太守の鶴の一声には逆らえぬ。
このことに限らず、宗春は竹越の杞憂(きゆう)を来たす命令を、既に多く発している。
宗春は、祭礼や祝いごとの規模を制限する倹約令を廃し、また武士の芝居見物の禁令を解いた。楽しみを与えるが藩主の務(つと)めと考えたゆえのことである。
夏の盛り。
御深井の丸は、名古屋城の北面に広がる、原生林を取りこんだ一郭である。
尾張初代藩主となる九男義(よし)直(なお)のために名古屋城を築いたとき、家康は城の北面に広がる湿地帯を「いざという時の逃げ場に」と教えた。
義直はその言葉を守り、湿地の中央の沼を掘り広げて東西三丁(一丁は一〇八メートル)、南北二丁の大池とし、南岸に小島築き、湿地を乾かした。岸辺にはあずまやや茶屋を設け、外からは判らぬように危急の際の退避、逃亡や立てこもりに必要な設備を施した。深井の森という原生林の中にも、密かに逃げ道を造った。一見、城主の風流のための一郭のように見えて、その実、城の秘密の中枢なのである。
御深井の丸には、何人(なんびと)も藩主の許可なく立ち入れぬ。
その日、宗春はみずから亭主となって、池端の茶屋の一つにしつらいをし、伊吹屋を朝茶に招いた。今日も暑くなるのだろう、深井の森の蝉(せみ)時雨(しぐれ)がはや、かしましい。障子は開け放してあるので一面の蓮(はす)の花が見渡せる。
茶室のにじり口があいた。やせた老人が、作法どおり狭い入り口を潜り抜け、客の座まで膝行(しっこう)した。
「お招き、ありがとうございます」
白扇を畳の縁外に置き、一揖(いちゆう)するのも作法にかなう。
(武士の出、というは確かなようじゃ)
宗春は風炉の釜にギヤマンの水差しから柄杓(ひしゃく)で数杯の水を差した。
水差しの蓋は、今朝宗春自身が、池で摘んだ緑鮮やかな蓮の葉である。床に活けてあるのも純白の蓮一輪。まだ開く前の蕾(つぼみ)である。
広口の、これもギヤマン造の夏茶碗に薄茶を立てた。蝉時雨が一段と高まる。息吹屋は自身膝行して碗をわが座に取り入れた。
「頂戴いたします」また一揖。
伊吹屋茂平は茶の心得並々ならぬと見える。
Posted by 渋柿 at 07:17 | Comments(0)
2009年01月13日
連載「尾張享元絵巻」5
襲封してすぐ、尾張藩江戸屋敷にあった宗春は、江戸城黒書院で八代将軍吉宗と御対顔を果たした。
「わが名より宗の一字を与える。これより宗春と名乗れ」これまで主計頭(かずえのかみ)通(みち)春(はる)と称していた宗春の、平伏した頭上に、力強い声が響いた
「ははっ」頭をあげて、吉宗の顔を見た。
宗春は、正徳三年(一七一三)先代将軍家継に拝謁して譜代衆(将軍直接の家来)となり、江戸城中に詰所(つめしょ)を賜(たまわ)った。また、二年前には吉宗自身によって、奥州梁川三万石を与えられている。吉宗とはこれが初対面ではなかったが、今までその顔をはっきりと見たことはなかった。
(ぷっ)噂どおり、美男とは程遠い、疱瘡(ほうそう)のあばたの残る異相であった。吉宗の生母は稀代(きだい)の醜女(しこめ)で、酔って手をつけた紀州三代光(みつ)貞(さだ)自身が、懐妊を告げられて狼狽したという話は名高い。しかも、身につけている衣服は、見るからに野暮ったい木綿物であった。
(田舎者じゃな)尾張家江戸屋敷で生まれ育った宗春である。元服まで江戸を知らず、紀州で育ったという吉宗に、ふと軽い侮(あなど)りを覚えた。
(城中の主となられてからも、倹約、倹約とのみおっしゃるそうじゃが・・)老中はじめ幕閣には、やはり木綿着用を命じ、絹物で御前に出た某老中を叱責したという話もあった。だが、御三家や大藩の大名には、未だ強制も叱責もない。
無論、宗春は熨斗目(のしめ)も袴も、つややかな絹物を着用している。服飾の趣味に自信のある宗春が、自ら選んだ今日の装いであった。
「余も、紀州(きしゅう)の末子に生まれ、兄達の早世で藩を継いだ。そちも長い部屋住み・・であったな」
「はっ」
自分と同じ、庶民と較べれば苦労とは言えないにしても・・部屋住みの冷や飯の味を知っている吉宗の言葉は、暖かく響いた。
「体をいとい、治世長く励んでくれい」尾張藩主の相次ぐ急病死をいっている。
「はっ、宗春身命をとしまして」 宗春は頬を紅潮させて応えた。
「時に・・」吉宗は宗春の、鮮やかな群青の熨斗目の袖を見た。「京の公(きん)達(だち)のように雅(みやび)なよそおいじゃな」
「はっ」
「美丈夫のそちによく似合うておる」
「恐れ入り奉ります」
「じゃがな、わが家は武門、ちと、そぐわぬやもなあ」
一瞬、宗春の背筋に、冷たいものが走った。
「いや、近頃は陸奥守も加賀宰相も、そのような色合いを好んでおる。今様のはやりじゃろうて」 そう言って、吉宗は笑顔を見せる。「くれぐれも、体をいとい、末永うの」
「はっ」
その御対顔の時のことを、宗春は太守として尾張に初入府してからも繰り返し夢に見た。
(よい歳をして夢にまで?)
宗春はそのたび苦笑する。
夢の中の吉宗の顔は・・兄に似て兄より慕わしいときがあり、また、瞬く間に父、兄、甥までを奪い去った死神に通ずる、恐ろしさを感じさせるときもあった。
「わが名より宗の一字を与える。これより宗春と名乗れ」これまで主計頭(かずえのかみ)通(みち)春(はる)と称していた宗春の、平伏した頭上に、力強い声が響いた
「ははっ」頭をあげて、吉宗の顔を見た。
宗春は、正徳三年(一七一三)先代将軍家継に拝謁して譜代衆(将軍直接の家来)となり、江戸城中に詰所(つめしょ)を賜(たまわ)った。また、二年前には吉宗自身によって、奥州梁川三万石を与えられている。吉宗とはこれが初対面ではなかったが、今までその顔をはっきりと見たことはなかった。
(ぷっ)噂どおり、美男とは程遠い、疱瘡(ほうそう)のあばたの残る異相であった。吉宗の生母は稀代(きだい)の醜女(しこめ)で、酔って手をつけた紀州三代光(みつ)貞(さだ)自身が、懐妊を告げられて狼狽したという話は名高い。しかも、身につけている衣服は、見るからに野暮ったい木綿物であった。
(田舎者じゃな)尾張家江戸屋敷で生まれ育った宗春である。元服まで江戸を知らず、紀州で育ったという吉宗に、ふと軽い侮(あなど)りを覚えた。
(城中の主となられてからも、倹約、倹約とのみおっしゃるそうじゃが・・)老中はじめ幕閣には、やはり木綿着用を命じ、絹物で御前に出た某老中を叱責したという話もあった。だが、御三家や大藩の大名には、未だ強制も叱責もない。
無論、宗春は熨斗目(のしめ)も袴も、つややかな絹物を着用している。服飾の趣味に自信のある宗春が、自ら選んだ今日の装いであった。
「余も、紀州(きしゅう)の末子に生まれ、兄達の早世で藩を継いだ。そちも長い部屋住み・・であったな」
「はっ」
自分と同じ、庶民と較べれば苦労とは言えないにしても・・部屋住みの冷や飯の味を知っている吉宗の言葉は、暖かく響いた。
「体をいとい、治世長く励んでくれい」尾張藩主の相次ぐ急病死をいっている。
「はっ、宗春身命をとしまして」 宗春は頬を紅潮させて応えた。
「時に・・」吉宗は宗春の、鮮やかな群青の熨斗目の袖を見た。「京の公(きん)達(だち)のように雅(みやび)なよそおいじゃな」
「はっ」
「美丈夫のそちによく似合うておる」
「恐れ入り奉ります」
「じゃがな、わが家は武門、ちと、そぐわぬやもなあ」
一瞬、宗春の背筋に、冷たいものが走った。
「いや、近頃は陸奥守も加賀宰相も、そのような色合いを好んでおる。今様のはやりじゃろうて」 そう言って、吉宗は笑顔を見せる。「くれぐれも、体をいとい、末永うの」
「はっ」
その御対顔の時のことを、宗春は太守として尾張に初入府してからも繰り返し夢に見た。
(よい歳をして夢にまで?)
宗春はそのたび苦笑する。
夢の中の吉宗の顔は・・兄に似て兄より慕わしいときがあり、また、瞬く間に父、兄、甥までを奪い去った死神に通ずる、恐ろしさを感じさせるときもあった。
Posted by 渋柿 at 18:41 | Comments(0)
2009年01月13日
連載「尾張享元絵巻」4
「寺社の、札・・」
「ただの木切れ、紙切れであろう。薬師(やくし)如来(にょらい)のお札も水(すい)天宮(てんぐう)のお札も、万病に効く、安産間違いなし、というて、数百年来売られておる。伊吹屋の伊吹御神湯とやらいうも、信心と同じよ。霊験(れいげん)あらたかな伊吹山の五木八草なりと固く信じて湯浴(ゆあ)みをして・・治る気の病もあろうよ。よほどの重病人でもなくば、蓬の湯に浸かってよもや体に害はあるまい。せいぜい風呂桶の傷みが早いというが関の山よ。土台、最初に銀一枚も出せる者に、その日暮らしの貧乏人はおらぬ道理ではないか。いわば金持ちの道楽、お上が費(つい)えの心配をしてやることもなかろうて。ただし、無理に講中にさそわれて金に困ったとか、断っても断っても勧められて困る、という訴えが一件でもあらばそのときは、考えねばならぬがのう」
「はっ」
「民(たみ)が納得ずくで高値の御神湯を求めるとあらば、いたし方はない。まこと万病に効くと信じて人に勧めるのも、止めることはなるまい。当人は誠心誠意、世のため人のためと信じているのであろうからのう。世に言う取退き無尽講とやらと違(ちご)うて、子、孫を募るものが一儲けしようなどと、さらさら考えもおらぬゆえ、騙られた、だまされたという訴えもなきことわりよ」
「万病に効くと信じて、病にかかりても御神湯に浸かり続けるばかりにて・・医者にかかったときには手遅れであった者も、この十年かなりおったはずと」
「それも、神信心と同じ、当人の考えの果てであろう。医者にも匙(さじ)違いでみすみす助かる命をあやめるということも現に皆無ではあるまい」
病気の治療法の選択は、自己責任である。自分を被害者と自覚する人間が、現実に存在していないのだ。行政は介入できぬ。これは宗春の堅い信念であった。
宗春は、昨年兄継友の死去により尾張藩第七代藩主となった。第三代藩主徳川綱(つな)誠(のり)の二十男・・本来、尾張の太守の座からはるか遠く、望むべくもない存在であった。ところが父の跡(あと)を継いだ長兄吉通(よしみち)、その長男五郎(ごろう)太(た)、そして夭折(ようせつ)した五郎太の跡を継いだ吉通の弟継友と、三代に亙(わた)る藩主が不審な急病で次々と死んで、宗春に藩主の座がめぐってきた。そこに幸運以上の何かがあったとのささやきが藩内外にあることも宗春は知っている
「身の運がただの幸運ではないとすれば、今の将軍家の強運も裏に何かあると申すか」
宗春は笑い飛ばした。八代将軍徳川吉宗(よしむね)。家格では尾張家に一歩を譲る紀州(きしゅう)家二代藩主徳川光(みつ)貞(さだ)の晩年の四男に生まれた。こちらも長兄、次兄の早世で藩主となり、七代将軍の八歳での夭折を受け、宗春の兄継友と競(せ)り勝って、まんまと八代将軍の座を射止めた。
身分低く寵(ちょう)薄い側室所生の末子という自分とよく似た出自に、宗春は吉宗に妙な親しみさえ感じている。
「ただの木切れ、紙切れであろう。薬師(やくし)如来(にょらい)のお札も水(すい)天宮(てんぐう)のお札も、万病に効く、安産間違いなし、というて、数百年来売られておる。伊吹屋の伊吹御神湯とやらいうも、信心と同じよ。霊験(れいげん)あらたかな伊吹山の五木八草なりと固く信じて湯浴(ゆあ)みをして・・治る気の病もあろうよ。よほどの重病人でもなくば、蓬の湯に浸かってよもや体に害はあるまい。せいぜい風呂桶の傷みが早いというが関の山よ。土台、最初に銀一枚も出せる者に、その日暮らしの貧乏人はおらぬ道理ではないか。いわば金持ちの道楽、お上が費(つい)えの心配をしてやることもなかろうて。ただし、無理に講中にさそわれて金に困ったとか、断っても断っても勧められて困る、という訴えが一件でもあらばそのときは、考えねばならぬがのう」
「はっ」
「民(たみ)が納得ずくで高値の御神湯を求めるとあらば、いたし方はない。まこと万病に効くと信じて人に勧めるのも、止めることはなるまい。当人は誠心誠意、世のため人のためと信じているのであろうからのう。世に言う取退き無尽講とやらと違(ちご)うて、子、孫を募るものが一儲けしようなどと、さらさら考えもおらぬゆえ、騙られた、だまされたという訴えもなきことわりよ」
「万病に効くと信じて、病にかかりても御神湯に浸かり続けるばかりにて・・医者にかかったときには手遅れであった者も、この十年かなりおったはずと」
「それも、神信心と同じ、当人の考えの果てであろう。医者にも匙(さじ)違いでみすみす助かる命をあやめるということも現に皆無ではあるまい」
病気の治療法の選択は、自己責任である。自分を被害者と自覚する人間が、現実に存在していないのだ。行政は介入できぬ。これは宗春の堅い信念であった。
宗春は、昨年兄継友の死去により尾張藩第七代藩主となった。第三代藩主徳川綱(つな)誠(のり)の二十男・・本来、尾張の太守の座からはるか遠く、望むべくもない存在であった。ところが父の跡(あと)を継いだ長兄吉通(よしみち)、その長男五郎(ごろう)太(た)、そして夭折(ようせつ)した五郎太の跡を継いだ吉通の弟継友と、三代に亙(わた)る藩主が不審な急病で次々と死んで、宗春に藩主の座がめぐってきた。そこに幸運以上の何かがあったとのささやきが藩内外にあることも宗春は知っている
「身の運がただの幸運ではないとすれば、今の将軍家の強運も裏に何かあると申すか」
宗春は笑い飛ばした。八代将軍徳川吉宗(よしむね)。家格では尾張家に一歩を譲る紀州(きしゅう)家二代藩主徳川光(みつ)貞(さだ)の晩年の四男に生まれた。こちらも長兄、次兄の早世で藩主となり、七代将軍の八歳での夭折を受け、宗春の兄継友と競(せ)り勝って、まんまと八代将軍の座を射止めた。
身分低く寵(ちょう)薄い側室所生の末子という自分とよく似た出自に、宗春は吉宗に妙な親しみさえ感じている。
Posted by 渋柿 at 07:28 | Comments(0)
2009年01月12日
連載「尾張享元絵巻」3
初夏である。名古屋城の背後にある広大な御深井(おふけ)の森から飛んできたのであろう、不如帰(ほととぎす)がしきりに鳴く。老鶯(おいうぐいす)も鳴き交わす。
青葉をわたってくる風も心地よい。
「その伊吹屋(いふきや)茂(も)平(へい)なるものが商売をはじめてより、もう・・」
「御先代(第六代藩主継(つぐ)友(とも))のころより、かれこれ十年にもあいなります」
「その商人(あきんど)、名古屋城下に参る前は、何をしておったのじゃ?」
「元は武士、親の代からの浪人らしゅうございます。何でも生来病弱で、伊吹山の神の霊験に縋(すが)らんと二十年、山に籠って薬草を採っておりましたそうな」
「それは・・眉唾(まゆつば)じゃの」
「はい。その上霊夢(れいむ)にて御神湯を伊吹の神より授けられたと申すのですから、全くもってその来歴、信は置けませぬ。・・というて、横目の調べでも二十年の山籠りが偽り事という確証もありませんで。とにかく、性質(たち)の悪い騙りに違いござりませぬ」
「とまれ、商いを始めてはや十年か。その間、お上に一件の騙られた、という訴えもないとはのう」
「はあ・・まことに無知蒙昧の下民には・・」
竹腰は、最前の嘆息を繰り返した。
「捨て置け」
宗春は、きっぱりと言った。
「はぁ?」
思わず竹腰は奇声をあげる。
「捨て、置くとは?」
「まずもって、騙られた、だまされたとの訴えは十年この方なかったのであろう」
「はあ」
「一応、五木八草を入れてもおる」
「しかし、その大部分はそのあたりの道端にいくらもある蓬や米糠などで・・」
「だが、誰もだまされたとは思っておらぬ。ねずみ算など寺子屋に一年も通ったものなどみな心得ておる今の世じゃ。講中の末の末、正価とやらでしか御神湯を買えぬものも、その値段で得心して買っておる。お上(かみ)が出るまでもない」
「では、みすみすの騙りを」
「では、寺社のお札のたぐいはどうじゃ」
青葉をわたってくる風も心地よい。
「その伊吹屋(いふきや)茂(も)平(へい)なるものが商売をはじめてより、もう・・」
「御先代(第六代藩主継(つぐ)友(とも))のころより、かれこれ十年にもあいなります」
「その商人(あきんど)、名古屋城下に参る前は、何をしておったのじゃ?」
「元は武士、親の代からの浪人らしゅうございます。何でも生来病弱で、伊吹山の神の霊験に縋(すが)らんと二十年、山に籠って薬草を採っておりましたそうな」
「それは・・眉唾(まゆつば)じゃの」
「はい。その上霊夢(れいむ)にて御神湯を伊吹の神より授けられたと申すのですから、全くもってその来歴、信は置けませぬ。・・というて、横目の調べでも二十年の山籠りが偽り事という確証もありませんで。とにかく、性質(たち)の悪い騙りに違いござりませぬ」
「とまれ、商いを始めてはや十年か。その間、お上に一件の騙られた、という訴えもないとはのう」
「はあ・・まことに無知蒙昧の下民には・・」
竹腰は、最前の嘆息を繰り返した。
「捨て置け」
宗春は、きっぱりと言った。
「はぁ?」
思わず竹腰は奇声をあげる。
「捨て、置くとは?」
「まずもって、騙られた、だまされたとの訴えは十年この方なかったのであろう」
「はあ」
「一応、五木八草を入れてもおる」
「しかし、その大部分はそのあたりの道端にいくらもある蓬や米糠などで・・」
「だが、誰もだまされたとは思っておらぬ。ねずみ算など寺子屋に一年も通ったものなどみな心得ておる今の世じゃ。講中の末の末、正価とやらでしか御神湯を買えぬものも、その値段で得心して買っておる。お上(かみ)が出るまでもない」
「では、みすみすの騙りを」
「では、寺社のお札のたぐいはどうじゃ」
Posted by 渋柿 at 18:09 | Comments(0)
2009年01月12日
連載「尾張享元絵巻」2
竹腰の配下の探索結果では、伊吹御神湯の原価は著しく安く、正価の七割近く値引きしても損をせぬどころか大儲(もう)けの値段を設定しているという。
また、客を講中に組織して客自身に新たな顧客獲得という営業活動をやらせるのであるから、支店も要らず、奉公人に払う給金もいらない。儲かるはずである。
これが名古屋城下だけではなく、尾張藩全土で、万病に効くとして売れ続けている。それだけでなく、
「どこそこの太物(ふともの)問屋(どんや)の隠居が、卒中でねたきりになって医者も見離したのに、御神湯のおかげで起きあがることが出来た」
「夫婦になって十三年、子宝に恵まれなかったどこそこの呉服屋夫婦に、御神湯のおかげで後継ぎが産まれた」
と、具体的な「効果」は枚挙(まいきょ)に暇(いとま)がない。
病気で死んだ者の通夜には、
「故人は、御神湯を勧(すす)めても信じなかったから・・」
死なずに済んだものを死ぬはめになった、といわんばかりの話が、大まじめでささやき交(か)わされる。
そんなに効くものなら尾張領内に死人は出なくなるはず、と竹腰は憤激している。
「しかもその五木八草もまやかしでございました」
と竹腰はまくし立てる。
古来貴人が愛用した「五木八草」の御神湯には、五木としては梅(うめ)、桃(もも)、柳(やなぎ)、桑(くわ)、桂(かつら)の皮、八草としては菖蒲(あやめ)、蓬(よもぎ)、繁縷(はこべら)、主(おも)奈美(なみ)、熊笹(くまざさ)、蓮(はす)、忍冬(すいかずら)の葉をよく乾燥させた物を細かく砕き薬(や)研(げん)で粉末にする。それを布袋に入れ、浴槽の湯に浸(ひた)すのである。
竹腰が藩のお抱え医師複数に鑑定させたところ、中身は柚子(ゆず)の実の皮、柳と桑の木の皮、松の葉と杉の葉、大庭子(おおばこ)、大根の葉、繁縷、そば粉、米糠(ぬか)、芹に蕪(かぶ)の葉が少量入ってはいるが大部分は蓬であった。しかも、薬研にかけて粉末にするどころか乾かした種々の草やら木の葉やらを、ざくざくと粗(あら)く切り刻んだだけだったという。
「これが三十袋はいって銀一枚でございます。その蓬はじめ、まがいの五木八草も、まことに伊吹山で摘んで、はるばる運んだものやら、どこの道端で摘んだものやら分かったものではございませぬ。さる金持ちが飼っております金魚の弱りました折人の万病に効くなら金魚にも効くはずと、その家の隠居が金魚鉢に御神湯の袋を投げ入れましたとか」
「して、金魚はいかがあいなった?」
竹腰は苦笑する。
「しばらく、苦しそうに喘(あえ)いでおりましたが、じき白い腹を上にして浮かんでまいったそうで」
「ぷっ」
宗春も、失笑した。
「水が濁りすぎたのだろうて。そば粉糠まで入っておればのう」
だがすぐに真顔になる。
「むーん」
銀一枚は建て前とはいえほぼ一両、当時の下女の給金が高給の江戸でさえ年四両に満たなかったことを考えれば、伊吹屋は、まやかしものを、法外の値段で、しかも騙りすれすれの方法で売って利益を得てきたことになる。
宗春は、また、しばし目を閉じた。
また、客を講中に組織して客自身に新たな顧客獲得という営業活動をやらせるのであるから、支店も要らず、奉公人に払う給金もいらない。儲かるはずである。
これが名古屋城下だけではなく、尾張藩全土で、万病に効くとして売れ続けている。それだけでなく、
「どこそこの太物(ふともの)問屋(どんや)の隠居が、卒中でねたきりになって医者も見離したのに、御神湯のおかげで起きあがることが出来た」
「夫婦になって十三年、子宝に恵まれなかったどこそこの呉服屋夫婦に、御神湯のおかげで後継ぎが産まれた」
と、具体的な「効果」は枚挙(まいきょ)に暇(いとま)がない。
病気で死んだ者の通夜には、
「故人は、御神湯を勧(すす)めても信じなかったから・・」
死なずに済んだものを死ぬはめになった、といわんばかりの話が、大まじめでささやき交(か)わされる。
そんなに効くものなら尾張領内に死人は出なくなるはず、と竹腰は憤激している。
「しかもその五木八草もまやかしでございました」
と竹腰はまくし立てる。
古来貴人が愛用した「五木八草」の御神湯には、五木としては梅(うめ)、桃(もも)、柳(やなぎ)、桑(くわ)、桂(かつら)の皮、八草としては菖蒲(あやめ)、蓬(よもぎ)、繁縷(はこべら)、主(おも)奈美(なみ)、熊笹(くまざさ)、蓮(はす)、忍冬(すいかずら)の葉をよく乾燥させた物を細かく砕き薬(や)研(げん)で粉末にする。それを布袋に入れ、浴槽の湯に浸(ひた)すのである。
竹腰が藩のお抱え医師複数に鑑定させたところ、中身は柚子(ゆず)の実の皮、柳と桑の木の皮、松の葉と杉の葉、大庭子(おおばこ)、大根の葉、繁縷、そば粉、米糠(ぬか)、芹に蕪(かぶ)の葉が少量入ってはいるが大部分は蓬であった。しかも、薬研にかけて粉末にするどころか乾かした種々の草やら木の葉やらを、ざくざくと粗(あら)く切り刻んだだけだったという。
「これが三十袋はいって銀一枚でございます。その蓬はじめ、まがいの五木八草も、まことに伊吹山で摘んで、はるばる運んだものやら、どこの道端で摘んだものやら分かったものではございませぬ。さる金持ちが飼っております金魚の弱りました折人の万病に効くなら金魚にも効くはずと、その家の隠居が金魚鉢に御神湯の袋を投げ入れましたとか」
「して、金魚はいかがあいなった?」
竹腰は苦笑する。
「しばらく、苦しそうに喘(あえ)いでおりましたが、じき白い腹を上にして浮かんでまいったそうで」
「ぷっ」
宗春も、失笑した。
「水が濁りすぎたのだろうて。そば粉糠まで入っておればのう」
だがすぐに真顔になる。
「むーん」
銀一枚は建て前とはいえほぼ一両、当時の下女の給金が高給の江戸でさえ年四両に満たなかったことを考えれば、伊吹屋は、まやかしものを、法外の値段で、しかも騙りすれすれの方法で売って利益を得てきたことになる。
宗春は、また、しばし目を閉じた。
Posted by 渋柿 at 09:58 | Comments(0)
2009年01月11日
連載「尾張享元絵巻」1
享保(きょうほう)十六年(一七三一)五月、尾張(おわり)名古屋城、本丸である。
藩主としてはじめて先月入国した徳川宗(むね)春(はる)は、付(つけ)家老・竹腰志摩守正武の報告を聞いていた。
宗春は、当年三十四歳であった。
襲封(しゅうふう)早々尾張藩江戸屋敷での遊芸音曲鳴り物を無制限に許可し、門の出入りも昼夜随意にしてしまった破天荒な殿様である。
初入国の行装も、これまでと打って変わって華麗(かれい)奇抜(きばつ)であった。
付家老としては、少々、いや大いに頭の痛いことを仕出かしそうな予感のする殿様である。
「まこと不届き、かと」
竹腰は上目遣いにいった。
「うむ」
宗春はしばし瞑目した。
「このようなものを万病に効くとは」
「だが、騙(かた)られたという届はあるのか?」
「それが、今だに一件もござらず。まことに無知蒙昧(もうまい)の下民には、あきれはてまする」
話題になっているのは「伊吹(いぶき)御神(ごしん)湯(とう)」と称する、今で言う入浴剤である。
伊吹山は近江(おうみ)と美濃(みの)国境にあり、昔から数々の薬草が採取されてきた。ゲンノショウコ、せんぶり、熊笹(くまざさ)等の薬草の宝庫であり、薬草は中腹に多い。中でも有名なものが灸(きゅう)のもぐさの原料となる蓬(よもぎ)である。
また、伊吹山は信仰の対象でもあった。
伊吹屋(いふきや)茂(も)平(へい)という名古屋城下に店を構える商人が、販売元である。
伊吹屋は、伊吹山で採った「五木八草」の薬草を混ぜ合わせたと称する粉末を、晒(さら)しの袋に包んで麗々しく包装したものを販売している。
その売り方がそもそもご禁制の取退(とりのき)き無尽講(むじんこう)ではないかと竹腰は立腹しているのであった。
「無論、横目(よこめ)に伊吹屋の商法は調べさせました」
竹腰は、膝(ひざ)を進めた。
伊吹屋が扱う「伊吹御神湯」の「正価」は銀一枚(含有量享保期四十三匁(もんめ))である。
銀五十匁で金一両、というのが幕府が定めた金銀の交換レートであるから、たかが入浴剤としては法外な値段であった。
「正価」で御神湯を買ったものは、自動的に「伊吹講」の講中として息吹屋の帳面に登録される。講中の者が新たに御神湯を購入する新講中を募れば、売上の一割二分がその者の懐に入る。そして、自身がまた御神湯を購入するときは、正価から一割二分引いた値段で買える。自分が「新講中」にした者がまた新たに「講中」を創れば最初の講中に正価の二割四分が支払われ、自身がまた購入するときの代金も正価の二割四分引きとなる。以下、子孫曾(ひ)孫と講中のピラミッドが出来ていけば、最終的には元親の講中に正価の六割までが転がり込む。購入代金も六割引きとなる。全くのねずみ算で講中は増える。
すぐに、新しく「講中」に誘う人間がいなくなる。行き詰まってしまう話である。
「六割引き」の優遇を実際に受けられるのはほんの一握り、ごく初期に「講中」になったものだけであるのは、理の当然である。
Posted by 渋柿 at 08:36 | Comments(1)