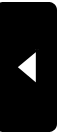2015年04月28日
鯰酔虎伝 3
落語は男が演るものとして作られ、磨き上げられてきた。女には難しい。女の噺なんて聞きたくない、という客も多い。だが、鯰の属する協会だって、女真打がもう四人もいる。
「俺ぁ、弟子は取らないよ」
こんなろくでなし、取れる訳がない。
「俺の齢、知ってるかい」
「はい」
「七十五だぜ」
「夕べ・・ほっとけませんでした」
「寝げろで窒息でもしやしないかってかい?そりゃ、親切なこった」
でもいいかい、俺ぁ入門してから真打になるまで十九年も掛かったんだ、よく考えなよ、あと十九年ていやあ、もうこの世にいる訳ねえだろ、と女の顔を見た。
「五十絡み、出来りゃあ四十代の師匠見つけるこったな」
「手間取ったのは、最初の師匠と反りが合わなかったからでしょう」
「まあな・・」
そうさ。今じゃ十年、当時だって十五年が昇進の相場だった。
「三道楽圓幽・・長楽亭京の輔と昭和の双璧だったけど、ばりばりの古典至上主義で」
「その二人、呼び捨てはして貰いたくねえな」
「すみません。鯰師匠、二つ目のときから新作で人気があったのに、真打の打診圓幽師匠が何度も握り潰したって」
「酒癖悪過ぎたからねえ。結局俺ぁ、駄目になっちまった噺家なんだよ」
「知ってます。出番貰っても勝手に抜いて、出たと思えば酒気帯び高座・・」
「出入り禁止も方々で喰らってる」
「あんな歌噺なんて、ありゃ寄席の鬼っ子だね・・ですか。香盤下げろとか、噺家辞めさせろとかいわれてるそうですね」
ああそうだよ、俺ぁ女房子泣かせて、挙句死なせた、最低の男って訳だ、悪いが帰ってくれ・・鯰は盆を持って立ち上がった。
「折角のお袋さんからの小包だ、持って帰りな。・・朝飯旨かったぜ、ありがとよ」
「鯰師匠で・・三十六人目なんです」
「えっ」
「三十五人の師匠方に、断られました」
桂家道丸、長楽亭京蔵、三道楽圓杖・・女は旬の噺家の名前を次々と挙げた。
いいね!
「俺ぁ、弟子は取らないよ」
こんなろくでなし、取れる訳がない。
「俺の齢、知ってるかい」
「はい」
「七十五だぜ」
「夕べ・・ほっとけませんでした」
「寝げろで窒息でもしやしないかってかい?そりゃ、親切なこった」
でもいいかい、俺ぁ入門してから真打になるまで十九年も掛かったんだ、よく考えなよ、あと十九年ていやあ、もうこの世にいる訳ねえだろ、と女の顔を見た。
「五十絡み、出来りゃあ四十代の師匠見つけるこったな」
「手間取ったのは、最初の師匠と反りが合わなかったからでしょう」
「まあな・・」
そうさ。今じゃ十年、当時だって十五年が昇進の相場だった。
「三道楽圓幽・・長楽亭京の輔と昭和の双璧だったけど、ばりばりの古典至上主義で」
「その二人、呼び捨てはして貰いたくねえな」
「すみません。鯰師匠、二つ目のときから新作で人気があったのに、真打の打診圓幽師匠が何度も握り潰したって」
「酒癖悪過ぎたからねえ。結局俺ぁ、駄目になっちまった噺家なんだよ」
「知ってます。出番貰っても勝手に抜いて、出たと思えば酒気帯び高座・・」
「出入り禁止も方々で喰らってる」
「あんな歌噺なんて、ありゃ寄席の鬼っ子だね・・ですか。香盤下げろとか、噺家辞めさせろとかいわれてるそうですね」
ああそうだよ、俺ぁ女房子泣かせて、挙句死なせた、最低の男って訳だ、悪いが帰ってくれ・・鯰は盆を持って立ち上がった。
「折角のお袋さんからの小包だ、持って帰りな。・・朝飯旨かったぜ、ありがとよ」
「鯰師匠で・・三十六人目なんです」
「えっ」
「三十五人の師匠方に、断られました」
桂家道丸、長楽亭京蔵、三道楽圓杖・・女は旬の噺家の名前を次々と挙げた。
いいね!
Posted by 渋柿 at 17:58 | Comments(0)
2015年04月26日
鯰酔虎伝 2
「薩長土肥の方の、肥前か」
「ええ、ばりばり、江戸っ子の仇」
「そりゃ、高座で嘯いてるだけさ」
噺家なんてだらしがない。戊辰の恨みと田舎者馬鹿にしたって、鹿児島・山口・高知・佐賀、呼ばれりゃどこでも機嫌を伺ってる。
飯椀を取り上げると、塩気は梅でという。白粥に大きな梅干しが一つ。種は除いてある。
「そうか・・塩、切らしてたんだ」
「・・何もなくて、びっくりしました」
「酒さえありゃ、いいんだ」
お茶が出る。三つ葉の浸しにゃあ微かに山椒の香りがした。女房が庭に植えておいてくれて雑草との競争に耐えてきた草木。それも、根こそぎブルトーザーが削っちまう。
それにしてもこの女、米味噌にお茶ッ葉まで持って、一体何しに来たんだ。
「師匠、楽屋口でも居酒屋でも申しましたが」
どうも昨日から一緒だったらしいけどな、こっちゃあ、何も覚えてねえんだよ!
「弟子にして下さい」
ぷっぷぷぅ、茶を吹いた。
「あんた、噺家になろうてのかい?」
真打の噺家は、弟子を取ることができる。噺家になる為の条件は唯一つ、真打の噺家に入門を許される事。他には何もない。
これは詰まらないものですが、と女は紙袋を差し出した。入門願いの手土産の積りらしい。中からは洒落じゃなくて、ちまちま小分けされた米味噌茶の葉に梅干しが出てくる。
「おととい、田舎の母から届きました。うち、農家なんです。伊万里には西九州一の梅園があって、これ、そこで採れた南高梅を母が漬けたんです。味噌だって手作りですよ。お茶も米も父と母が作ってて・・」
「これで、さっきの朝飯、作ってくれたのか」
とんだ手土産に、手ぇ付けちまった。
「明日から、こちらに通ってよろしいでしょうか?親も承知しておりますので、すぐにでも、電話で挨拶させます」
(よく知ってやがる)
入門には、原則として親の同意が要る。
「正気の沙汰じゃ、ねえな」
「女だからですか?」
どう答えるか、迷った。
「ええ、ばりばり、江戸っ子の仇」
「そりゃ、高座で嘯いてるだけさ」
噺家なんてだらしがない。戊辰の恨みと田舎者馬鹿にしたって、鹿児島・山口・高知・佐賀、呼ばれりゃどこでも機嫌を伺ってる。
飯椀を取り上げると、塩気は梅でという。白粥に大きな梅干しが一つ。種は除いてある。
「そうか・・塩、切らしてたんだ」
「・・何もなくて、びっくりしました」
「酒さえありゃ、いいんだ」
お茶が出る。三つ葉の浸しにゃあ微かに山椒の香りがした。女房が庭に植えておいてくれて雑草との競争に耐えてきた草木。それも、根こそぎブルトーザーが削っちまう。
それにしてもこの女、米味噌にお茶ッ葉まで持って、一体何しに来たんだ。
「師匠、楽屋口でも居酒屋でも申しましたが」
どうも昨日から一緒だったらしいけどな、こっちゃあ、何も覚えてねえんだよ!
「弟子にして下さい」
ぷっぷぷぅ、茶を吹いた。
「あんた、噺家になろうてのかい?」
真打の噺家は、弟子を取ることができる。噺家になる為の条件は唯一つ、真打の噺家に入門を許される事。他には何もない。
これは詰まらないものですが、と女は紙袋を差し出した。入門願いの手土産の積りらしい。中からは洒落じゃなくて、ちまちま小分けされた米味噌茶の葉に梅干しが出てくる。
「おととい、田舎の母から届きました。うち、農家なんです。伊万里には西九州一の梅園があって、これ、そこで採れた南高梅を母が漬けたんです。味噌だって手作りですよ。お茶も米も父と母が作ってて・・」
「これで、さっきの朝飯、作ってくれたのか」
とんだ手土産に、手ぇ付けちまった。
「明日から、こちらに通ってよろしいでしょうか?親も承知しておりますので、すぐにでも、電話で挨拶させます」
(よく知ってやがる)
入門には、原則として親の同意が要る。
「正気の沙汰じゃ、ねえな」
「女だからですか?」
どう答えるか、迷った。
Posted by 渋柿 at 18:15 | Comments(0)
2015年04月25日
鯰酔虎伝 1
「あんまりいい世間でも・・なかったなぁ」
ちょっと待っておくんなさい、最期の見納めだ・・屋敷の門から娑婆を見る。
何やっても甲斐性なし。金の無いのは首の無いのと同じってねえ。いっそ売っ払っちまおう。首代は七両二分、そう、間男堪忍と同じさ。刀の試し斬り?上等だ。すぱっと遣ってくんな、但し、お代は前金だ。
「お前さん」女房の声がする。
「お前さん、御飯だよ、お前さんってば」
うるせい、商売の邪魔だ。
味噌の香。お前さん、女房が頭を揺すった。
(うわっ)
痛い。夢・・か。薄く、眼を開けた。くすんだ天井に壁の、ここは間違いなく俺の家、感心に・・ちゃんと帰ってはきてる。
「大丈夫ですか、師匠」
何だい他人行儀な、お前さんと呼べよ。
「もう、十時過ぎましたよ」
ここにまだ・・未練か。来週には出てかなくちゃならない。お前も夢に出張って味噌汁の一つ、作りたくなるのも無理ねえな。
「今日は寄席、ないんですか?」
ねえよ、あるわけねえだろ。
「明日も?」
「ああ」
「明後日も?」
「九月の中席まで、空いてらあ」
枕元をごそごそ、老眼鏡を探る。どうも女房のさつきじゃあねえ様だ。
「随分召し上がってたんで、お粥にしました」
Gパンに薄緑のTシャッ、こいつぁ誰なんだ。万年床から起き上がったが・・判らない。
卓袱台なんて気の利いた物はない。味噌汁に白粥の盆は、畳にじか置き。ゆんべの酒で荒れている筈の胃の腑が、きゅっと鳴いた。あんた誰?と訊くのは後回しにして箸を取る。
「こいつぁ、まるで茗荷の宿だねぇ」
初夏のこの季節、宿屋の主が金目当てに物忘れさせようと茗荷責め。が、客が忘れたのは宿賃払いだった、というのがオチの噺だ。
「庭に生えてた茗荷とか、使いました」
それでか・・味噌汁の実もお浸しも茗荷、それに三つ葉。懐かしい香りがする訳だ。
汁を、一口啜る。
「こりゃ・・煮干しの出汁かい?」
鰹節や昆布じゃない。勿論旨味調味料でも。
「いりこ、です。・・煮干しの事、うちの田舎じゃそう呼ぶんです。肥前松浦のいりこ」
お粥、茗荷、煮干し・・アクセントが微妙に違うのは、そういう訳か。
「松浦てえと、平戸?あの本所七不思議の」
怪談噺くらいしか、思い浮かばない。
「いえ、上屋敷落葉なしの椎の平戸新田は、長崎県。うちその割と近くなんですけど境越えてて・・肥前佐賀の伊万里です」
ちょっと待っておくんなさい、最期の見納めだ・・屋敷の門から娑婆を見る。
何やっても甲斐性なし。金の無いのは首の無いのと同じってねえ。いっそ売っ払っちまおう。首代は七両二分、そう、間男堪忍と同じさ。刀の試し斬り?上等だ。すぱっと遣ってくんな、但し、お代は前金だ。
「お前さん」女房の声がする。
「お前さん、御飯だよ、お前さんってば」
うるせい、商売の邪魔だ。
味噌の香。お前さん、女房が頭を揺すった。
(うわっ)
痛い。夢・・か。薄く、眼を開けた。くすんだ天井に壁の、ここは間違いなく俺の家、感心に・・ちゃんと帰ってはきてる。
「大丈夫ですか、師匠」
何だい他人行儀な、お前さんと呼べよ。
「もう、十時過ぎましたよ」
ここにまだ・・未練か。来週には出てかなくちゃならない。お前も夢に出張って味噌汁の一つ、作りたくなるのも無理ねえな。
「今日は寄席、ないんですか?」
ねえよ、あるわけねえだろ。
「明日も?」
「ああ」
「明後日も?」
「九月の中席まで、空いてらあ」
枕元をごそごそ、老眼鏡を探る。どうも女房のさつきじゃあねえ様だ。
「随分召し上がってたんで、お粥にしました」
Gパンに薄緑のTシャッ、こいつぁ誰なんだ。万年床から起き上がったが・・判らない。
卓袱台なんて気の利いた物はない。味噌汁に白粥の盆は、畳にじか置き。ゆんべの酒で荒れている筈の胃の腑が、きゅっと鳴いた。あんた誰?と訊くのは後回しにして箸を取る。
「こいつぁ、まるで茗荷の宿だねぇ」
初夏のこの季節、宿屋の主が金目当てに物忘れさせようと茗荷責め。が、客が忘れたのは宿賃払いだった、というのがオチの噺だ。
「庭に生えてた茗荷とか、使いました」
それでか・・味噌汁の実もお浸しも茗荷、それに三つ葉。懐かしい香りがする訳だ。
汁を、一口啜る。
「こりゃ・・煮干しの出汁かい?」
鰹節や昆布じゃない。勿論旨味調味料でも。
「いりこ、です。・・煮干しの事、うちの田舎じゃそう呼ぶんです。肥前松浦のいりこ」
お粥、茗荷、煮干し・・アクセントが微妙に違うのは、そういう訳か。
「松浦てえと、平戸?あの本所七不思議の」
怪談噺くらいしか、思い浮かばない。
「いえ、上屋敷落葉なしの椎の平戸新田は、長崎県。うちその割と近くなんですけど境越えてて・・肥前佐賀の伊万里です」
Posted by 渋柿 at 15:24 | Comments(0)
2015年02月22日
こわい
多分・・・お母さんやおばあちゃんと、家で餅つきをした経験などない方だと思います。
「かたくて食べられない」
返品の要請 搗き立てでも30分もすれば硬くなるのがもち米100パーセント、前日研いで水に浸した餅。
それは当然の理解と思っていました。
しかし、和菓子屋のでんぷん等を混ぜた、数日たってもやわらかい「餅」しか商品価値はないと確信していらっしゃる模様。
その方以後のクレームはなく完売しましたが・・・これから種々のイベント、餅つきなど見たこともないという方が多数派になったら・・・怖いと思いました。
(本当の杵つき餅を販売できません)
「かたくて食べられない」
返品の要請 搗き立てでも30分もすれば硬くなるのがもち米100パーセント、前日研いで水に浸した餅。
それは当然の理解と思っていました。
しかし、和菓子屋のでんぷん等を混ぜた、数日たってもやわらかい「餅」しか商品価値はないと確信していらっしゃる模様。
その方以後のクレームはなく完売しましたが・・・これから種々のイベント、餅つきなど見たこともないという方が多数派になったら・・・怖いと思いました。
(本当の杵つき餅を販売できません)
Posted by 渋柿 at 20:20 | Comments(0)
2015年02月03日
2015年02月02日
一喝
「結局、最優秀作でも佳作でもないしぃ」
「起居不自由、失語症の家族もいるしぃ」
先輩の一喝
コンテストに応募して、賞をいただいたのなら、表彰式に出席するのは受賞者として義務
眼が覚めましたぁ Σd(≧∀≦*)
「起居不自由、失語症の家族もいるしぃ」
先輩の一喝
コンテストに応募して、賞をいただいたのなら、表彰式に出席するのは受賞者として義務
眼が覚めましたぁ Σd(≧∀≦*)
Posted by 渋柿 at 17:56 | Comments(0)
2014年12月16日
12月16日の記事
84歳の母と有田町白川の錦秋彩る有田ダムを訪れました。母は、背後の黒髪山天童岩と、水辺に突き出す通称ひょうたん島の位置を確認します。「ここよ」。山水画のうな景色の中、彫刻の乙女が佇む辺りから、湖水を指さしました。手にした古いアルバムには、坊主頭の男の子やもんぺの女の子たち。昭和31年、有田小学校に勤めていた母の、飯盒はんごう炊爨すいさんのスナップです。当時黒髪山から流れる川はひょうたん島の岩を巡り、白川の集落へと注いでいたそうです。
青磁の色の湖水は曾て盆地状の広場で、鎮西八郎為朝が大蛇退治の策を練ったという伝説から「評定場」と呼ばれ、昭和15年頃には雑木を払うなど整備もなされて、冬には雪合戦、子供たちの格好の遊び場でした。
「ご飯の出来具合や火の始末に神経使ったけど、子供たちは喜んだねえ」
今は、ダムを巡る道に掛かる橋の一つに残る「評定橋」の名と、陶板の「為朝大蛇退治伝説」碑だけが、昔を偲ぶよすがです。昭和28年の大水害を期に計画された多目的ダムが35年に竣工、評定場も、湖底に沈みました。
「もう、この子たちも70ねぇ」母が呟きました。
青磁の色の湖水は曾て盆地状の広場で、鎮西八郎為朝が大蛇退治の策を練ったという伝説から「評定場」と呼ばれ、昭和15年頃には雑木を払うなど整備もなされて、冬には雪合戦、子供たちの格好の遊び場でした。
「ご飯の出来具合や火の始末に神経使ったけど、子供たちは喜んだねえ」
今は、ダムを巡る道に掛かる橋の一つに残る「評定橋」の名と、陶板の「為朝大蛇退治伝説」碑だけが、昔を偲ぶよすがです。昭和28年の大水害を期に計画された多目的ダムが35年に竣工、評定場も、湖底に沈みました。
「もう、この子たちも70ねぇ」母が呟きました。
Posted by 渋柿 at 14:29 | Comments(0)
2014年11月28日
2014年11月18日
2014年11月15日
わけもわからず・・・
ほうれん草の発芽は難しい。特に九月、土の温度が高いときには発芽率が低い。
一度失敗し、二度目。堆肥を振って耕した畝に、一昼夜水に浸した種を、不発芽を見越して暑く播いた。
結果の、大量発芽。
直売所でも、全部はさばけなかった。
十月末に出っくわして、わけもわからず大量のほうれん草を押し付けられた方々・・・申し訳ありません。
一度失敗し、二度目。堆肥を振って耕した畝に、一昼夜水に浸した種を、不発芽を見越して暑く播いた。
結果の、大量発芽。
直売所でも、全部はさばけなかった。
十月末に出っくわして、わけもわからず大量のほうれん草を押し付けられた方々・・・申し訳ありません。
Posted by 渋柿 at 20:29 | Comments(0)
2014年02月12日
二里町誌
早春の昼下がり訪れた、伊万里市民図書館。伊万里学コーナー書架の最上段に、金文字の背表紙も鮮やかな分厚い「二里町誌」がありました。図書館の蔵書は二冊で、貸出可の本はちょうど貸出中でした。昨年春の出版以来、問い合わせも多く、館内外で沢山の方が閲覧されたそうです。

【二里公民館作成ポスター】
ふるさとの二里の町誌が二里公民館で編纂されていると聞いたのは、息子が生まれた頃でした。編纂の取り組みは1979年から始まっていたそうです。その後、伊万里市市史編纂のため余儀なく中断。委員の物故が相次ぎ、四人の委員で出版されたのは、息子が大学を卒業した2013年でした。樹齢400年の古子滝藤をあしらったポスターに心躍りました。
購読した町内外の方から「よくこれだけのものが出来ましたね」という声が寄せられたそうです。
昭和42年の大水害で変貌する前の二里町の姿を記憶しているのは、50代の私の世代まででしょう。
伊万里と有田に挟まれた村落が激動の日本の歴史の中でたどった、埋もれるには惜しい歩みの記録です。目を通されてみてはいかがでしょうか。
【二里公民館作成ポスター】
ふるさとの二里の町誌が二里公民館で編纂されていると聞いたのは、息子が生まれた頃でした。編纂の取り組みは1979年から始まっていたそうです。その後、伊万里市市史編纂のため余儀なく中断。委員の物故が相次ぎ、四人の委員で出版されたのは、息子が大学を卒業した2013年でした。樹齢400年の古子滝藤をあしらったポスターに心躍りました。
購読した町内外の方から「よくこれだけのものが出来ましたね」という声が寄せられたそうです。
昭和42年の大水害で変貌する前の二里町の姿を記憶しているのは、50代の私の世代まででしょう。
伊万里と有田に挟まれた村落が激動の日本の歴史の中でたどった、埋もれるには惜しい歩みの記録です。目を通されてみてはいかがでしょうか。
Posted by 渋柿 at 20:31 | Comments(0)
2014年02月10日
2014年01月26日
2014年01月17日
2014年01月16日
初夏の落葉終章
「芸人は、顔と名前憶えて貰えるのが一番。おかみさん、啖呵ぁ切ってまで長楽亭左京の名をこの世に繫ぎ留めた。夫婦の絆は二世、情愛は深いてえことを申します。今日は、そんな噺にお付き合い願います」
あの日、ここにいらした方もあるでしょう、左京が十年前に、ここで演った噺でもあります・・襟を摘まみ、上手の床に手を伸ばした。
「お前さん、起きとくれよぅ・・」
マクラが長かった分、少し端折って入った。
「芝浜」。酔漢・財布・芝浜・・圓朝の即興三題噺から百余年、幾世代もかけて噺家が磨き上げた、屈指の古典落語。
(ええっ?普通、ここで拍手湧くかぁ?)
本当にこういう所は、どう転ぶか判らない。
「お願いだよ、起きとくれってば、河岸行ってくれなきゃ、釜の蓋が開かないんだよ」
女房が、飲んだくれの亭主に哀願している。
・・左京、起きてくれ、起きてくれよう、真打昇進試験、始まっちまうよぅ・・
半泣きの声がした。十六年前の俺だ。兄弟子の家で夜が明け、悪ふざけがとんでもない結果になり、みんなで青くなっている。うるさい!左京は寝返りを打って背中を向けた。
・・誰だこんなに飲ませたの、俺じゃねえぞ、おい、起きてくれ、破門されちまうぞ、昇進試験だよ、起きてくれ左京、間に合わないよぅ・・仕方ない、殴るぞ・・
左京、お前本当に、自分の事全部判ってたのか。今生きてたらどんな落語演るんだろう。見たかった。才能も欠点もみんな合わさって、お前は稀有の噺家だったんだ。
「起きとくれってんだよぅ、お前さん」
「うるせいな、もっと寝かせろい」
「だってもう、十日も河岸いってないんだよ」
無意識に、左京の間、になっている。
あちこち、頷いている客がいた。きっと十年前、ここで左京の高座を聞いていたんだ。ホールの室温が上昇していくのが、肌で判る。
(あの日・・)
開演前、着替えを済ませた左京は、楽屋の窓から、ホールを囲む楠の樹々を見ていた。
(いってたな・・不思議な樹ですね、兄さん。冬を耐えたんでしょうに、若葉が萌えるそばで、ほら、落ち葉が散ってます・・って)
残る桜も散る桜、違うか、こんな一番いい季節に、葉を散らす樹もあるんですねえ・・左京が見ていたのは、初夏の落葉だった。
「判ったよ。起きてやるから、まず飲みてえだけ飲ませろ」
左京が真向いの席にいて、苦笑混じりに聞いている様な気がした。
あの日、ここにいらした方もあるでしょう、左京が十年前に、ここで演った噺でもあります・・襟を摘まみ、上手の床に手を伸ばした。
「お前さん、起きとくれよぅ・・」
マクラが長かった分、少し端折って入った。
「芝浜」。酔漢・財布・芝浜・・圓朝の即興三題噺から百余年、幾世代もかけて噺家が磨き上げた、屈指の古典落語。
(ええっ?普通、ここで拍手湧くかぁ?)
本当にこういう所は、どう転ぶか判らない。
「お願いだよ、起きとくれってば、河岸行ってくれなきゃ、釜の蓋が開かないんだよ」
女房が、飲んだくれの亭主に哀願している。
・・左京、起きてくれ、起きてくれよう、真打昇進試験、始まっちまうよぅ・・
半泣きの声がした。十六年前の俺だ。兄弟子の家で夜が明け、悪ふざけがとんでもない結果になり、みんなで青くなっている。うるさい!左京は寝返りを打って背中を向けた。
・・誰だこんなに飲ませたの、俺じゃねえぞ、おい、起きてくれ、破門されちまうぞ、昇進試験だよ、起きてくれ左京、間に合わないよぅ・・仕方ない、殴るぞ・・
左京、お前本当に、自分の事全部判ってたのか。今生きてたらどんな落語演るんだろう。見たかった。才能も欠点もみんな合わさって、お前は稀有の噺家だったんだ。
「起きとくれってんだよぅ、お前さん」
「うるせいな、もっと寝かせろい」
「だってもう、十日も河岸いってないんだよ」
無意識に、左京の間、になっている。
あちこち、頷いている客がいた。きっと十年前、ここで左京の高座を聞いていたんだ。ホールの室温が上昇していくのが、肌で判る。
(あの日・・)
開演前、着替えを済ませた左京は、楽屋の窓から、ホールを囲む楠の樹々を見ていた。
(いってたな・・不思議な樹ですね、兄さん。冬を耐えたんでしょうに、若葉が萌えるそばで、ほら、落ち葉が散ってます・・って)
残る桜も散る桜、違うか、こんな一番いい季節に、葉を散らす樹もあるんですねえ・・左京が見ていたのは、初夏の落葉だった。
「判ったよ。起きてやるから、まず飲みてえだけ飲ませろ」
左京が真向いの席にいて、苦笑混じりに聞いている様な気がした。
Posted by 渋柿 at 09:06 | Comments(0)
2014年01月15日
初夏の落葉17
死なない奴はいない。そろそろ、心構えだけは必要だろう。左京の享年を、去年越えた。
今思えばかなり前から、変調は自覚していたんだろう。打ち上げでも飲まなくなってた。
それでいて、悲壮感や辛さを、最後まで微塵も見せなかった。誰にも真実を告げず、十数分のネタで、静かに高座を降りていった。
(綺麗事が過ぎまっせ、左京さん、ええかっこしいや・・か)
骨あげの時の柳小夢の呟きは、同い齢の同志を失った哀しみに溢れていた。
その小夢も翌年の晩秋、癌で散る。左京とほぼ同じ、死の十一日前まで高座に上がり、一時間を越える「地獄八景亡者戯」をやり遂げた。それが最後のネタとなった。
仲間に全て事情を明かし、途中で力尽きたら続きは頼むと、頭を下げていたそうである。楽屋に医者を待機させて、直前まで酸素吸入をしながらサゲまで語り切った。
大きな動きはなくとも、死後の世界を茶化しまくる噺に客は爆笑したという。
伝説の西口広場を彷彿とさせる芸人魂。左京を見届けた上での・・それが西の噺家、東とはまた違う、最後の高座の意地だったのだろう。
(左京の置き土産は、小夢さんだけじゃない)
俺達には勿論、若手にも強烈だった。稽古の時左京に貰った扇子や手拭いを、今も御守り代わりにしている若手は多い。カゼとマンダラは侍でいえば両刀、噺家の魂なのだ。
最後に楽屋入りした時は、もう自分で足袋も履けなくなっていた。左京がおいそこの二つ目、頼むよ、なんて嘯いたのはそれが初めてだった。居合わせた桂家道介が、帯まで結んでやっていた。
さっきはありがとよ・・「六尺棒」で使ったばかりの噺家の魂を、左京は道介に託した。
その道介は、葬式の日、寄席の客席で左京の姿を確かに見たという。
真打昇進を果たした道介が、披露興行の演目に混ぜた新作は、寄席の度肝を抜いた。
(代演で高座に出た中堅が癌で突然死、生涯最後の高座が前座噺入門級「寿限無」という、情けない事に・・か)
持ちネタに定着したから何度も聞いた。よくできている。虚実入り混じって芸人の悲哀を描き、しかも泣かせない。大いに笑わせる。
近頃は忙しい合間を縫い、癌検診に行く噺家も増えた。寄席内外にカミングアウトして、抗癌剤を使いながら高座を勤める者もいる。
(不謹慎ていう人もいるけど・・)
古典落語だって、死や葬式を洒落のめしている。建前の道学蹴飛ばすのが落語だ。化けたな道介・・左京ならきっとそういうだろう。根っからの芸人だったから。
今思えばかなり前から、変調は自覚していたんだろう。打ち上げでも飲まなくなってた。
それでいて、悲壮感や辛さを、最後まで微塵も見せなかった。誰にも真実を告げず、十数分のネタで、静かに高座を降りていった。
(綺麗事が過ぎまっせ、左京さん、ええかっこしいや・・か)
骨あげの時の柳小夢の呟きは、同い齢の同志を失った哀しみに溢れていた。
その小夢も翌年の晩秋、癌で散る。左京とほぼ同じ、死の十一日前まで高座に上がり、一時間を越える「地獄八景亡者戯」をやり遂げた。それが最後のネタとなった。
仲間に全て事情を明かし、途中で力尽きたら続きは頼むと、頭を下げていたそうである。楽屋に医者を待機させて、直前まで酸素吸入をしながらサゲまで語り切った。
大きな動きはなくとも、死後の世界を茶化しまくる噺に客は爆笑したという。
伝説の西口広場を彷彿とさせる芸人魂。左京を見届けた上での・・それが西の噺家、東とはまた違う、最後の高座の意地だったのだろう。
(左京の置き土産は、小夢さんだけじゃない)
俺達には勿論、若手にも強烈だった。稽古の時左京に貰った扇子や手拭いを、今も御守り代わりにしている若手は多い。カゼとマンダラは侍でいえば両刀、噺家の魂なのだ。
最後に楽屋入りした時は、もう自分で足袋も履けなくなっていた。左京がおいそこの二つ目、頼むよ、なんて嘯いたのはそれが初めてだった。居合わせた桂家道介が、帯まで結んでやっていた。
さっきはありがとよ・・「六尺棒」で使ったばかりの噺家の魂を、左京は道介に託した。
その道介は、葬式の日、寄席の客席で左京の姿を確かに見たという。
真打昇進を果たした道介が、披露興行の演目に混ぜた新作は、寄席の度肝を抜いた。
(代演で高座に出た中堅が癌で突然死、生涯最後の高座が前座噺入門級「寿限無」という、情けない事に・・か)
持ちネタに定着したから何度も聞いた。よくできている。虚実入り混じって芸人の悲哀を描き、しかも泣かせない。大いに笑わせる。
近頃は忙しい合間を縫い、癌検診に行く噺家も増えた。寄席内外にカミングアウトして、抗癌剤を使いながら高座を勤める者もいる。
(不謹慎ていう人もいるけど・・)
古典落語だって、死や葬式を洒落のめしている。建前の道学蹴飛ばすのが落語だ。化けたな道介・・左京ならきっとそういうだろう。根っからの芸人だったから。
Posted by 渋柿 at 16:06 | Comments(0)
2014年01月14日
初夏の落葉16
豊島演芸場の客席は九十五。特に平日の昼席、客が十人前後という芝居も多かった。八百人入るホールでの落語会で、客五人という経験もした。つい最近まで、やっつ・ここのつを越えて二ケタのお客に、つばなれしてると喜んだ。
百万・・途方もない「お客様数」だ。
(お前のガンバレは確かに芸術品だよ、左京)
左京と過ごした日々は、もう遙か遠い。
(飲めってんだよ、この兄弟子野郎・・か)
散々、凄まれた。噺は飛びぬけてテンポよく明るいくせに、有り余る才とさがの狷介が酒を荒ませるのは、鯰と似ていた。
(しらふの時は、兄さんって立ててたけど)
京蔵は高校卒業後すぐに京治の門を叩いた。左京は大学出、それも卒業数年後の入門だ。
(・・やりにくかったなあ)
何しろこの「弟弟子」は、こっちがまだランドセル背負ってた頃には、高校落研の花形として活躍していたのだ。入門した時点で、もう七十以上の古典のネタを上げていた。
(二年・・いつも、一緒だった)
兄の様な弟弟子、他の世界ではありえない、不思議な関係。師匠に叱られるのも一緒だし、こっそりの息抜きも一緒。酒も左京に鍛えられた。そして落語を熱く語った。そんな俺達を、師匠は厳しく、温かく見守っていた。
あたしの弟子は、みんな優秀だと思っております、そう挨拶した京治師匠は、左京の葬儀の半年後、亡くなった。期待を寄せていた左京を失った衝撃が、命を縮めたという人もいる。いう人は、いえばいい。
(みんな、優秀なんだ・・俺も)
卑下したりしたら、師匠に失礼だ。芸人は自惚れの塊、それがなくなりゃあやめなきゃしょうがない・・左京もいっていた。
「左京に稽古を付けて貰ってた若手が、今あたし達を脅かしてて・・何億の遺産貰った様なもんです。いや、流石にそこまではないか」
一部、笑いが取れた。
真打昇進試験の時だって、お天道様西から登っても左京が落ちる訳はないと思っていた。だから、前祝いだとどんどん飲ませたのだ。
(最初は一杯だけなんていってて、とんでもない事になっちまった)
それでも左京は実力で、不合格を覆した。
「今の時代新作なんかに目もくれず、八っつぁんかい、こっちいお入りなんて、古典一筋でしょ。まあ左京も相当の臍曲がりでしたよ」
あの才能に、新作に逃げる必要など全くなかった。持ちネタの多さとその完成度を、良くできた食堂のサンプルと揶揄した奴がいる。あれが死んだ作り物か?冗談じゃない。
そんな左京だったから、あの「ガンパレ」には度肝を抜かれた。狂気さえ覗く高座は、そこにいた者全ての脳天をぶちのめしていた。
(これが・・左京か)
卓越した話術と歌唱力、楽屋で大酒喰らったというが、それはむしろ狂う為。二つの強烈な個性、一期一会の化学変化。
「ガンバレ」を作ったのは鯰、古典にしたのは・・左京だ。
「ガンバレは世に残りましたけど、まさか一回こっきりの高座がアクセス百万なんて。あいつも目え回してるでしょう、あの世で」
神様は、左京や京治師匠には、ぴか一の華を与えた。でも、俺や鯰師匠にも、それぞれちゃんと別の贈り物をくれたのだ。
(俺の最後の高座は、どうなるのかなぁ?)
百万・・途方もない「お客様数」だ。
(お前のガンバレは確かに芸術品だよ、左京)
左京と過ごした日々は、もう遙か遠い。
(飲めってんだよ、この兄弟子野郎・・か)
散々、凄まれた。噺は飛びぬけてテンポよく明るいくせに、有り余る才とさがの狷介が酒を荒ませるのは、鯰と似ていた。
(しらふの時は、兄さんって立ててたけど)
京蔵は高校卒業後すぐに京治の門を叩いた。左京は大学出、それも卒業数年後の入門だ。
(・・やりにくかったなあ)
何しろこの「弟弟子」は、こっちがまだランドセル背負ってた頃には、高校落研の花形として活躍していたのだ。入門した時点で、もう七十以上の古典のネタを上げていた。
(二年・・いつも、一緒だった)
兄の様な弟弟子、他の世界ではありえない、不思議な関係。師匠に叱られるのも一緒だし、こっそりの息抜きも一緒。酒も左京に鍛えられた。そして落語を熱く語った。そんな俺達を、師匠は厳しく、温かく見守っていた。
あたしの弟子は、みんな優秀だと思っております、そう挨拶した京治師匠は、左京の葬儀の半年後、亡くなった。期待を寄せていた左京を失った衝撃が、命を縮めたという人もいる。いう人は、いえばいい。
(みんな、優秀なんだ・・俺も)
卑下したりしたら、師匠に失礼だ。芸人は自惚れの塊、それがなくなりゃあやめなきゃしょうがない・・左京もいっていた。
「左京に稽古を付けて貰ってた若手が、今あたし達を脅かしてて・・何億の遺産貰った様なもんです。いや、流石にそこまではないか」
一部、笑いが取れた。
真打昇進試験の時だって、お天道様西から登っても左京が落ちる訳はないと思っていた。だから、前祝いだとどんどん飲ませたのだ。
(最初は一杯だけなんていってて、とんでもない事になっちまった)
それでも左京は実力で、不合格を覆した。
「今の時代新作なんかに目もくれず、八っつぁんかい、こっちいお入りなんて、古典一筋でしょ。まあ左京も相当の臍曲がりでしたよ」
あの才能に、新作に逃げる必要など全くなかった。持ちネタの多さとその完成度を、良くできた食堂のサンプルと揶揄した奴がいる。あれが死んだ作り物か?冗談じゃない。
そんな左京だったから、あの「ガンパレ」には度肝を抜かれた。狂気さえ覗く高座は、そこにいた者全ての脳天をぶちのめしていた。
(これが・・左京か)
卓越した話術と歌唱力、楽屋で大酒喰らったというが、それはむしろ狂う為。二つの強烈な個性、一期一会の化学変化。
「ガンバレ」を作ったのは鯰、古典にしたのは・・左京だ。
「ガンバレは世に残りましたけど、まさか一回こっきりの高座がアクセス百万なんて。あいつも目え回してるでしょう、あの世で」
神様は、左京や京治師匠には、ぴか一の華を与えた。でも、俺や鯰師匠にも、それぞれちゃんと別の贈り物をくれたのだ。
(俺の最後の高座は、どうなるのかなぁ?)
Posted by 渋柿 at 16:46 | Comments(0)
2014年01月13日
初夏の落葉15
六年後。四月二九日、佐賀市文化会館大ホール、夕顔亭鯰・長楽亭京蔵落語二人会。
「鯰師匠、八十過ぎとは思えません。時代がやっと鯰に追いつきました」
トリの京蔵が、高座で話し出す。
「四十年前、高座で立ち上がっただけで破門でした。近頃じゃ命知らずの若手が逆立ちまでやってて・・先程の噺、ガンバレっていうんですけど、もう古典落語でいいです」
どっと受ける。
「大酒飲んでなぜか長生き、お呼びがあれば全国どこでも飛び回る夕顔亭鯰八十一歳。現役最高齢更新も、視野に入ってまいりました」
いかにも枯れた、古風な佇まいの老噺家が、立って踊って毒を吐き、高らかに歌い倒す。客は呆気に取られ、爆笑し、最後の「ガンバレ」のサゲには盛大な拍手が湧いていた。
「福岡まではよく来るんですけど、あたしが佐賀にお邪魔するのは十年振りです。そん時は弟弟子との二人会でございました」
カチガラスてんですか、パトカーみたいなのも初めて見まして、とご当地を持ち上げる。
「ちょうど今時分で、楠の燃える様な若葉が綺麗でした。楠の栄える国だからさがっていうんだって、意外と物知りな弟弟子が教えてくれたのを・・覚えております」
羽織の紐を解き、静かに脱いだ。
「この弟弟子、それから間もなく患い付いちまいまして。ええ、うちの師匠京治も今年七回忌ですが、同じ年、半年前に逝った長楽亭左京てのが、その物知りなんでございますよ」
湿っぽいマクラに、客席は白けている。構うものか、寄席とは違い、立前座の時間制限はかからない。たとえマクラで終わったって、今日七回忌の左京を語りたかった。
「有志の方々がご尽力くださいまして、左京追悼のCDが世に出ました。実は左京、生前一度だけ、ガンバレ演らされてましてねえ。葬式ん時そのビデオ流して大騒ぎになって、追悼CDにも収録されたんです」
そりゃあもう、大変でした・・京蔵は客席の白けを無視した。
「おかみさん、左京がガンバレっていい残したって、絶対に譲らない。参りました」
最期は手前にまで、サゲ付けやがった。「たがや」の「たがやあぁ」・・頑張らないと嘯いてた奴の最期、口を付いた言葉は「ガンバレ」。それが「ガンバレ」のサゲだった。
笑い事ではない。香盤だけは結構高い鯰も是非にと口を添え、連休のくそ忙しい中、ビデオ映像探し回らなければならなかった。
「うちの師匠は、ガンバレなんてよせやい、古典の名手だった左京の葬式だ、古典で送ろう、いっその事、最後の高座で送ってやりたいって、ぶつぶついってましたけど」
その録音はある。間と抑揚は確かに面目躍如。でも声は、往年の左京とは似ても似つかない。
最後の高座にあのネタ「六尺棒」を選んだ訳は、判る気がする。小憎らしい馬鹿息子と大甘の頑固親父・・あれは多分親父さんへの、詫びと感謝だ。入門の時の騒動は、俺も似たようなもの。
師匠は化けやがったぜと満足そうだったけど、これを化けたといやあ何だかお前が化けて出そうだ。
左京、勘弁してくれ。俺はまだ、師匠程の落語の耳がないんだろう。天下の京治が兜脱いだんだ、お前の最後の高座「六尺棒」は、きっと空前絶後の落語だったんだろう。
「おかみさん、お言葉ですがうちの人は古典の名手なんかじゃあございません、憚りながら落語の、名手だったんでございますってねえ・・あの、長楽亭京治に向かって啖呵ぁ切った。これにゃあ師匠も二の句が継げなくって・・惚れた欲目てえのは、本当に怖ろしい」
笑っていいのか、客は困惑している。
(相変わらず、だなぁ)
地方では生の落語を聞く機会など、年にそう何度もないのだろう。豊島の常連客の様な、阿吽の呼吸は望めない。やっぱり違いますね、けど、どう転ぶか皆目見当つかないてのも面白かったですよ・・左京も苦笑していた。
皆様木戸銭を払ってお入りになっております、と京蔵は六分程の入りの客席を見る。
「世の中著作権てえものがある事はご案内と思いますが、最近、CDを動画投稿する方がいらして、噺家はおまんまの食い上げです」
ここでやっと、客が笑った。
「まあ左京を埋もれさせちゃあ勿体ないんで、堅い事もいえない。あれで元祖鯰師匠も復活したんだってもっぱらの噂で。師匠は絶対そんな事ぁないって、意地張ってますけどね」
鯰へ向けてだろう、拍手が起こる。
「兎に角今日現在、ガンバレ左京バージョンの再生数、何と百万を超えております。中にゃあ、ガンバレの動画で初めて長楽亭左京を知った、ずっと前に亡くなってたと判ってびっくりした、なんてえ方も結構たくさんいらっしゃいますしねえ」
「鯰師匠、八十過ぎとは思えません。時代がやっと鯰に追いつきました」
トリの京蔵が、高座で話し出す。
「四十年前、高座で立ち上がっただけで破門でした。近頃じゃ命知らずの若手が逆立ちまでやってて・・先程の噺、ガンバレっていうんですけど、もう古典落語でいいです」
どっと受ける。
「大酒飲んでなぜか長生き、お呼びがあれば全国どこでも飛び回る夕顔亭鯰八十一歳。現役最高齢更新も、視野に入ってまいりました」
いかにも枯れた、古風な佇まいの老噺家が、立って踊って毒を吐き、高らかに歌い倒す。客は呆気に取られ、爆笑し、最後の「ガンバレ」のサゲには盛大な拍手が湧いていた。
「福岡まではよく来るんですけど、あたしが佐賀にお邪魔するのは十年振りです。そん時は弟弟子との二人会でございました」
カチガラスてんですか、パトカーみたいなのも初めて見まして、とご当地を持ち上げる。
「ちょうど今時分で、楠の燃える様な若葉が綺麗でした。楠の栄える国だからさがっていうんだって、意外と物知りな弟弟子が教えてくれたのを・・覚えております」
羽織の紐を解き、静かに脱いだ。
「この弟弟子、それから間もなく患い付いちまいまして。ええ、うちの師匠京治も今年七回忌ですが、同じ年、半年前に逝った長楽亭左京てのが、その物知りなんでございますよ」
湿っぽいマクラに、客席は白けている。構うものか、寄席とは違い、立前座の時間制限はかからない。たとえマクラで終わったって、今日七回忌の左京を語りたかった。
「有志の方々がご尽力くださいまして、左京追悼のCDが世に出ました。実は左京、生前一度だけ、ガンバレ演らされてましてねえ。葬式ん時そのビデオ流して大騒ぎになって、追悼CDにも収録されたんです」
そりゃあもう、大変でした・・京蔵は客席の白けを無視した。
「おかみさん、左京がガンバレっていい残したって、絶対に譲らない。参りました」
最期は手前にまで、サゲ付けやがった。「たがや」の「たがやあぁ」・・頑張らないと嘯いてた奴の最期、口を付いた言葉は「ガンバレ」。それが「ガンバレ」のサゲだった。
笑い事ではない。香盤だけは結構高い鯰も是非にと口を添え、連休のくそ忙しい中、ビデオ映像探し回らなければならなかった。
「うちの師匠は、ガンバレなんてよせやい、古典の名手だった左京の葬式だ、古典で送ろう、いっその事、最後の高座で送ってやりたいって、ぶつぶついってましたけど」
その録音はある。間と抑揚は確かに面目躍如。でも声は、往年の左京とは似ても似つかない。
最後の高座にあのネタ「六尺棒」を選んだ訳は、判る気がする。小憎らしい馬鹿息子と大甘の頑固親父・・あれは多分親父さんへの、詫びと感謝だ。入門の時の騒動は、俺も似たようなもの。
師匠は化けやがったぜと満足そうだったけど、これを化けたといやあ何だかお前が化けて出そうだ。
左京、勘弁してくれ。俺はまだ、師匠程の落語の耳がないんだろう。天下の京治が兜脱いだんだ、お前の最後の高座「六尺棒」は、きっと空前絶後の落語だったんだろう。
「おかみさん、お言葉ですがうちの人は古典の名手なんかじゃあございません、憚りながら落語の、名手だったんでございますってねえ・・あの、長楽亭京治に向かって啖呵ぁ切った。これにゃあ師匠も二の句が継げなくって・・惚れた欲目てえのは、本当に怖ろしい」
笑っていいのか、客は困惑している。
(相変わらず、だなぁ)
地方では生の落語を聞く機会など、年にそう何度もないのだろう。豊島の常連客の様な、阿吽の呼吸は望めない。やっぱり違いますね、けど、どう転ぶか皆目見当つかないてのも面白かったですよ・・左京も苦笑していた。
皆様木戸銭を払ってお入りになっております、と京蔵は六分程の入りの客席を見る。
「世の中著作権てえものがある事はご案内と思いますが、最近、CDを動画投稿する方がいらして、噺家はおまんまの食い上げです」
ここでやっと、客が笑った。
「まあ左京を埋もれさせちゃあ勿体ないんで、堅い事もいえない。あれで元祖鯰師匠も復活したんだってもっぱらの噂で。師匠は絶対そんな事ぁないって、意地張ってますけどね」
鯰へ向けてだろう、拍手が起こる。
「兎に角今日現在、ガンバレ左京バージョンの再生数、何と百万を超えております。中にゃあ、ガンバレの動画で初めて長楽亭左京を知った、ずっと前に亡くなってたと判ってびっくりした、なんてえ方も結構たくさんいらっしゃいますしねえ」
Posted by 渋柿 at 16:40 | Comments(0)
2014年01月12日
初夏の落葉14
ぽとり、顔に温かいものが落ちた。
目を開くと、あかねの顔があった。
「お前さん」
(ここは・・)
数日前、息を引き取った病室だった。
(違う・・夢見てたんだ)
ぴっぴっぴ、ベッドの脇のモニターが、下がり続ける血圧と心拍数を示している。
死ぬのはこれから、夢というより臨死体験か。それが死神と人情噺たあ、職業病にも程があるよな。兎に角、色んなネタがごっちゃになってた。まあ弔いで「ガンバレ」流すなんて、夢じゃなきゃあり得ない事か・・。
「夜が明けたみたい。・・大丈夫、ミミの餌はちゃんと置いてきたから」
窓辺の樹の影が、寄席の切り絵の様だ。ほんのり明るい空を背に、枝が揺れている。
(し、ししょ・・)
もうあかねは、唇の動きだけを読んでいる。
「師匠は大阪。小夢さんとこの落語会」
そうだった。リアル世界じゃ、今日のうちに駆けつけるのは無理だ。かき入れ時の連休、しかもアウエーでは代演は利かない。すぐ来てくれるのは、やっぱり鯰師匠くらいかな。
(俺も、小夢さんに誘われてたっけ。病み上がりでも前座噺なら何とかなるだろうって)
事態を隠してたから、断れなかった。馬鹿だよ。結局豊島の代演で力尽きた。これでよかったんだ。この体で大阪まで辿り着けたとしても、出ない声で、それも寿限無の途中でぶっ倒れてりゃ、与太郎だろう。
(師匠が東京に戻るまで、葬式はやっぱり延ばさなきゃ。・・あんまり無理するなよ)
前座二つ目は弔い慣れしてる。俺もやって来た。遠慮するなお互い様だ、任せればいい。
(な、なま・・)
「え?何?」
鯰師匠だけにゃあ酒を出すな、特に火葬場じゃ絶対にだめだぞ、そういい残しておきたいが・・無理の様だ。
(す・・ま・・)
入門の時釘を刺されたし、こっちは承知の上でこの世界に飛び込んだけど、お前にまで馬鹿な苦労をさせちまった。入りの悪い豊島が一番好き、客に呼ばれても酌もしない、救いようのない臍曲りでさ。テレビ仕事なんか滅多に受けなくて。人から見りゃ時代錯誤の、滑稽な野郎だったろうな。
「済まないなんていわないで。お前さんと一緒になれて、本当によかった」
そうかなあ・・他人と喧嘩ばかりしてきた。
(古典になったネタは初めから完成度が高いんだ、新作で一度は笑った客でもな、二度も三度もまた来て聞くか?・・か)
新作なんて一過性のもんですぐに消えちまう、そう信じて古典一筋にやってきた。どの古典ネタだってできた時はみんな新作だなんていう奴には、ムキになって絡み倒した。
風を入れるね、あかねは立ち上がって窓を開ける。楠の若葉の薫りがした。
(あ・・り・・)
ありがとう。・・でも結局、死ぬのが怖くて高座にしがみ付いてただけかもしれない。疼痛緩和のお蔭でぎりぎりまで続けられたけど、医者代薬代諸々、随分かかったんだろ。今度の請求書は個室料まで込みときてる。
ごめんよ。俺は残念ながら、古典になって残る程の噺家じゃなかった。忘れられる。
(いいじゃない、お噺上手のただのお爺さんと、噺好きのお婆さんになるのも・・か)
それさえ叶わなかった。甲斐はなかったな、あんなに尽くしてくれたのに。
(こ・こ・・)
ここにいてくれ。目が霞んでる。最後にお前の顔を、瞼に焼き付けておきたい。あかねは椅子に戻って、お前さん、と微笑んだ。
(ほ・れ、て・た・・)
そうだ、その笑顔が見たかった。綺麗だ。声失くす前に、いってやりゃあよかった。
本当に赤だったかな?いや、「小鍛冶」を弾く振袖は、絶対あかね色じゃなきゃいけない。俺はお前に、心底惚れていた。
「お前さん!」
呼吸が切迫した。か?が?えっ何?何かいおうとしている。がん?がんば?
あかねは、ナースコールを押した。
「五時二一分、ご臨終です」
脈を取り瞳孔を見た医者がいう。
サゲが、付いた。楠の葉鳴りは楽日のハネ太鼓。風が吹く。枝が揺れる。拍手が続く。
窓から、初夏の落ち葉が一枚、舞い込んだ。
目を開くと、あかねの顔があった。
「お前さん」
(ここは・・)
数日前、息を引き取った病室だった。
(違う・・夢見てたんだ)
ぴっぴっぴ、ベッドの脇のモニターが、下がり続ける血圧と心拍数を示している。
死ぬのはこれから、夢というより臨死体験か。それが死神と人情噺たあ、職業病にも程があるよな。兎に角、色んなネタがごっちゃになってた。まあ弔いで「ガンバレ」流すなんて、夢じゃなきゃあり得ない事か・・。
「夜が明けたみたい。・・大丈夫、ミミの餌はちゃんと置いてきたから」
窓辺の樹の影が、寄席の切り絵の様だ。ほんのり明るい空を背に、枝が揺れている。
(し、ししょ・・)
もうあかねは、唇の動きだけを読んでいる。
「師匠は大阪。小夢さんとこの落語会」
そうだった。リアル世界じゃ、今日のうちに駆けつけるのは無理だ。かき入れ時の連休、しかもアウエーでは代演は利かない。すぐ来てくれるのは、やっぱり鯰師匠くらいかな。
(俺も、小夢さんに誘われてたっけ。病み上がりでも前座噺なら何とかなるだろうって)
事態を隠してたから、断れなかった。馬鹿だよ。結局豊島の代演で力尽きた。これでよかったんだ。この体で大阪まで辿り着けたとしても、出ない声で、それも寿限無の途中でぶっ倒れてりゃ、与太郎だろう。
(師匠が東京に戻るまで、葬式はやっぱり延ばさなきゃ。・・あんまり無理するなよ)
前座二つ目は弔い慣れしてる。俺もやって来た。遠慮するなお互い様だ、任せればいい。
(な、なま・・)
「え?何?」
鯰師匠だけにゃあ酒を出すな、特に火葬場じゃ絶対にだめだぞ、そういい残しておきたいが・・無理の様だ。
(す・・ま・・)
入門の時釘を刺されたし、こっちは承知の上でこの世界に飛び込んだけど、お前にまで馬鹿な苦労をさせちまった。入りの悪い豊島が一番好き、客に呼ばれても酌もしない、救いようのない臍曲りでさ。テレビ仕事なんか滅多に受けなくて。人から見りゃ時代錯誤の、滑稽な野郎だったろうな。
「済まないなんていわないで。お前さんと一緒になれて、本当によかった」
そうかなあ・・他人と喧嘩ばかりしてきた。
(古典になったネタは初めから完成度が高いんだ、新作で一度は笑った客でもな、二度も三度もまた来て聞くか?・・か)
新作なんて一過性のもんですぐに消えちまう、そう信じて古典一筋にやってきた。どの古典ネタだってできた時はみんな新作だなんていう奴には、ムキになって絡み倒した。
風を入れるね、あかねは立ち上がって窓を開ける。楠の若葉の薫りがした。
(あ・・り・・)
ありがとう。・・でも結局、死ぬのが怖くて高座にしがみ付いてただけかもしれない。疼痛緩和のお蔭でぎりぎりまで続けられたけど、医者代薬代諸々、随分かかったんだろ。今度の請求書は個室料まで込みときてる。
ごめんよ。俺は残念ながら、古典になって残る程の噺家じゃなかった。忘れられる。
(いいじゃない、お噺上手のただのお爺さんと、噺好きのお婆さんになるのも・・か)
それさえ叶わなかった。甲斐はなかったな、あんなに尽くしてくれたのに。
(こ・こ・・)
ここにいてくれ。目が霞んでる。最後にお前の顔を、瞼に焼き付けておきたい。あかねは椅子に戻って、お前さん、と微笑んだ。
(ほ・れ、て・た・・)
そうだ、その笑顔が見たかった。綺麗だ。声失くす前に、いってやりゃあよかった。
本当に赤だったかな?いや、「小鍛冶」を弾く振袖は、絶対あかね色じゃなきゃいけない。俺はお前に、心底惚れていた。
「お前さん!」
呼吸が切迫した。か?が?えっ何?何かいおうとしている。がん?がんば?
あかねは、ナースコールを押した。
「五時二一分、ご臨終です」
脈を取り瞳孔を見た医者がいう。
サゲが、付いた。楠の葉鳴りは楽日のハネ太鼓。風が吹く。枝が揺れる。拍手が続く。
窓から、初夏の落ち葉が一枚、舞い込んだ。
Posted by 渋柿 at 07:58 | Comments(0)
2014年01月10日
初夏の落葉13
「行けば、判る。・・神様に愛され過ぎたんだよ、お前は」
「そう、自惚れとくよ」
「弔辞でもいってたじゃないか」
「口と肚は、別だ。ざまァ見ろって思ってた奴だって、いたかもしれない」
「情けない事いってくれるな。忙しい時期に、あれだけの人が駆けつけてくれたんだ。あれがただの空涙なら、酔狂も大概じゃないか」
そうだ、二十年やった答えが、降りやまぬ雨に香華を手向けてくれた、あの長い列だ。
「道丸も小夢さんもみんな泣いてくれた・・」
ツン・ツン・ツン、遠くで音がする。祭囃子?それにしてはずっと拍も節も重い。三味より哀しい、心にしみる音。琴、だ。
ツン・テン・シャン、ツン・テン・シャン、はっきりと耳に馴染んだ旋律になっていく。
「これは・・」
「小鍛冶・・お前の囃子だな」
噺家の出囃子は、長唄のサビの部分を使う事が多い。「小鍛冶」も、元々は能の演目で、長唄に取り入れられた。筝曲用に編曲されたのは、そう古い事ではない。
(あかね・・)
出逢った日の、そうだ、ありゃあ確か赤い振袖だったか、スポットライトを浴びて、舞台の上に、あかねがいた。
「弾いてるよ、たった一人んなった家ん中で。・・おかみさん、ここまで音を届けるたあ、よっぽどあんたに思いが深いんだなあ」
「・・一目惚れ、だった」
邦楽の会の司会の仕事で、出逢った。
反対を押し切って一緒になった時から、真打になったら出囃子は、あの日あかねが弾いた「小鍛冶」だと、心に決めていた。
琴の音は、緩く速く続いている。
左京さんなんていうな、噺家の女房ならお前さんだろと関白ぶった新婚の頃。恥じらいながらそう呼んだ初々しい声が、耳に甦る。
(俺は、馬鹿だ・・)
死神が許してくれた最後の時間、ぎりぎりまであかねの側に居てやらなきゃならなかったんだ。俺は最後の最後まで、落語の世界しか見ていなかった。馬鹿だ、大馬鹿野郎だ。
「寂しいんだよ。猫しかいない、思い出がまだ生々しい家に居るのは」
「そう・・だろうな」
「葬式も四十九日、百か日も大変だけど、そりゃ哀しむ暇、なくす知恵かもしれないぜ」
余韻を残して、琴がやむ。
「かみさんの所に、戻りたいか?」
「今更何だよ」
「戻りたいんだろ。・・おまえんちに反魂香が・・ある訳ないよなあ」
「反魂香がありゃ、戻れるんだな」
「あるのか。それ、おかみさんに何とかして焚いて貰えりゃあ・・」
「稽古ん時のテープじゃ、駄目か?」
「反魂香」は、死んだ人と逢えるという噺。
テープじゃねえ・・死神は溜息をつき、暫く考えていた。
「判ったよ。かみさんと居られるのはほんのちょっとだけだけど、勘弁してくれ」
死神は、下に垂れた蝋の欠片を拾い始めた。
「まあ、あんまり当てにはしねえ事だな。なんせ時間を戻すなんて今までやった事あない」
「そんな事をして、お前・・」
「オプションが付くっていっただろうが。疫病神にでも、塵でも芥でもなってやらあ」
落語の神様は残酷だ、何でお前に道半ばの寿命しかないんだよう、死神は居直る。
「そりゃ俺だって・・見てたっていってたな、布団掻き毟って呻いて、さ・・」
俺のとことん情けない姿も、こいつだけは知っている。
「だけどもういい。・・ありがとう。お蔭でネタの形見分けだってできたし・・」
何より燃え尽きる直前、精一杯輝けたんだ。
十月余一会に割り込み復帰第一声、夢落ちネタの「鼠穴」を演じた。二月までは、定席にも通しで出る事ができた。ホール落語も新年の帝立劇場の「厩火事」と二月の台東座「浜野矩随」。定席はもう無理になってからも、三月にはラジオ真打競演「猫の皿」を収録し、豊島余一会で「井戸の茶碗」。そして最後の高座、代演の「六尺棒」は、あの師匠が化けたと、初めて褒めてくれたんだ。
(結局、騙した事になるんだけど・・)
贔屓客は、左京再起と本当に喜んでくれた。
「二十五の俺が決めた通りに、死ねたんだよ」
「やせ我慢はよせ。かみさんのとこ、戻りたいんだろう・・戻りな」
「やせ我慢・・か」
「今度こそ、お前に惚れてたっていうんだぞ」
「・・ああ」
死神は帯の毛羽を抜いて、握り固めた欠片の芯にした。手近な炎で炙り、蝋を芯に浸み込ませる。出来上がった蝋燭もどきに、何やらじっと念を込めてから火を灯した。
「目を閉じるんだ」
あじゃらかもくれん・あかね・まい・すぃいとはぁと・・死神が呪文を唱える。
「そう、自惚れとくよ」
「弔辞でもいってたじゃないか」
「口と肚は、別だ。ざまァ見ろって思ってた奴だって、いたかもしれない」
「情けない事いってくれるな。忙しい時期に、あれだけの人が駆けつけてくれたんだ。あれがただの空涙なら、酔狂も大概じゃないか」
そうだ、二十年やった答えが、降りやまぬ雨に香華を手向けてくれた、あの長い列だ。
「道丸も小夢さんもみんな泣いてくれた・・」
ツン・ツン・ツン、遠くで音がする。祭囃子?それにしてはずっと拍も節も重い。三味より哀しい、心にしみる音。琴、だ。
ツン・テン・シャン、ツン・テン・シャン、はっきりと耳に馴染んだ旋律になっていく。
「これは・・」
「小鍛冶・・お前の囃子だな」
噺家の出囃子は、長唄のサビの部分を使う事が多い。「小鍛冶」も、元々は能の演目で、長唄に取り入れられた。筝曲用に編曲されたのは、そう古い事ではない。
(あかね・・)
出逢った日の、そうだ、ありゃあ確か赤い振袖だったか、スポットライトを浴びて、舞台の上に、あかねがいた。
「弾いてるよ、たった一人んなった家ん中で。・・おかみさん、ここまで音を届けるたあ、よっぽどあんたに思いが深いんだなあ」
「・・一目惚れ、だった」
邦楽の会の司会の仕事で、出逢った。
反対を押し切って一緒になった時から、真打になったら出囃子は、あの日あかねが弾いた「小鍛冶」だと、心に決めていた。
琴の音は、緩く速く続いている。
左京さんなんていうな、噺家の女房ならお前さんだろと関白ぶった新婚の頃。恥じらいながらそう呼んだ初々しい声が、耳に甦る。
(俺は、馬鹿だ・・)
死神が許してくれた最後の時間、ぎりぎりまであかねの側に居てやらなきゃならなかったんだ。俺は最後の最後まで、落語の世界しか見ていなかった。馬鹿だ、大馬鹿野郎だ。
「寂しいんだよ。猫しかいない、思い出がまだ生々しい家に居るのは」
「そう・・だろうな」
「葬式も四十九日、百か日も大変だけど、そりゃ哀しむ暇、なくす知恵かもしれないぜ」
余韻を残して、琴がやむ。
「かみさんの所に、戻りたいか?」
「今更何だよ」
「戻りたいんだろ。・・おまえんちに反魂香が・・ある訳ないよなあ」
「反魂香がありゃ、戻れるんだな」
「あるのか。それ、おかみさんに何とかして焚いて貰えりゃあ・・」
「稽古ん時のテープじゃ、駄目か?」
「反魂香」は、死んだ人と逢えるという噺。
テープじゃねえ・・死神は溜息をつき、暫く考えていた。
「判ったよ。かみさんと居られるのはほんのちょっとだけだけど、勘弁してくれ」
死神は、下に垂れた蝋の欠片を拾い始めた。
「まあ、あんまり当てにはしねえ事だな。なんせ時間を戻すなんて今までやった事あない」
「そんな事をして、お前・・」
「オプションが付くっていっただろうが。疫病神にでも、塵でも芥でもなってやらあ」
落語の神様は残酷だ、何でお前に道半ばの寿命しかないんだよう、死神は居直る。
「そりゃ俺だって・・見てたっていってたな、布団掻き毟って呻いて、さ・・」
俺のとことん情けない姿も、こいつだけは知っている。
「だけどもういい。・・ありがとう。お蔭でネタの形見分けだってできたし・・」
何より燃え尽きる直前、精一杯輝けたんだ。
十月余一会に割り込み復帰第一声、夢落ちネタの「鼠穴」を演じた。二月までは、定席にも通しで出る事ができた。ホール落語も新年の帝立劇場の「厩火事」と二月の台東座「浜野矩随」。定席はもう無理になってからも、三月にはラジオ真打競演「猫の皿」を収録し、豊島余一会で「井戸の茶碗」。そして最後の高座、代演の「六尺棒」は、あの師匠が化けたと、初めて褒めてくれたんだ。
(結局、騙した事になるんだけど・・)
贔屓客は、左京再起と本当に喜んでくれた。
「二十五の俺が決めた通りに、死ねたんだよ」
「やせ我慢はよせ。かみさんのとこ、戻りたいんだろう・・戻りな」
「やせ我慢・・か」
「今度こそ、お前に惚れてたっていうんだぞ」
「・・ああ」
死神は帯の毛羽を抜いて、握り固めた欠片の芯にした。手近な炎で炙り、蝋を芯に浸み込ませる。出来上がった蝋燭もどきに、何やらじっと念を込めてから火を灯した。
「目を閉じるんだ」
あじゃらかもくれん・あかね・まい・すぃいとはぁと・・死神が呪文を唱える。
Posted by 渋柿 at 17:46 | Comments(0)